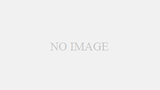平成25年(ワ)第16709号
原 告
被 告 アンシス・ジャパン株式会社
平成27(2015)年3月4日
東京地方裁判所
民事第36部Aい係 御中
原告訴訟代理人弁護士 志 村 新
準備書面(最終)
はじめに
(1) 被告は,原告による本訴請求について,時間外・休日労働(以下たんに「時間外労働」という)に対する未払割増賃金にかかる請求部分に関するものを含めて全 面的に争い続けたが,全ての争点についての証拠調べを終了した後である本年2月12日に至り,時間外労働に対する未払割増賃金にかかる部分の請求を認諾するにいたった。
この部分にかかる請求を基礎づける事実についての争いは,原告の時間外労働の時間数という単純なものであった。ところが,被告は,原告をはじめとする従業員らの実労働時間の客観的な把握が容易であるにもかかわらず,これを一切行ってこなかった。そして,本訴においては,原告の対象期間中における時間外労働の存在を全面的に否定し続けた末に,証拠調べ終了後に至ってこの部分の請求を認諾するにいたったのである。これは要するに,労働基準法違反の犯罪行為に該当する事実を隠蔽するとともに同法所定の付加金の支払いを免れるために行ったものであろう。
(2)そこで,本書面においては,その余の請求(債務不履行乃至不法行為による損害賠償請求)について,証拠調べの結果を踏まえつつ,これを裏付ける事実及び原告の請求が認容されるべきことを述べることとする。
なお,この被告による原告に対する債務不履行乃至不法行為を基礎づける事実としては,被告が原告の時間外労働の実態を把握せずこれに対する割増賃金の支払いを怠り続けてきたという労働基準法違反の事実,さらにはその後も本訴係属中も含めてこれらの違法行為を隠蔽しようと試み続けてきた事実もまた,その悪質性からこれに該当するものである(なお,東京地方裁判所平成25年(ワ)第6497号事件についての同裁判所民事第4部平成27年2月27日判決も,時間外労働を認識しながらこれについての割増賃金の支払を怠った事案について「当然の義務を懈怠して……支払をしなかった行為は,不法行為を構成するものと認められる。」と断じている。)。従って,それらに関する事実の詳細についても後記「第6」(24頁以下)において述べることとする。
(3)被告が上記の点以外の事実経過を否定するために描こうとしてきた構図は,概要,以下のようなものであった。
すなわち,①訴外Kにはコミュニケーション能力にやや問題があり社内コミュニケーションに多少の支障を生じることがあったものの業務に支障があった訳ではなかった,②被告は原告の再入社にさいしての採用にあたって事前に原告に対し訴外Kのコミュニケーション能力にやや問題があること等を説明し原告の了解を得ていた,③にもかかわらず,原告は,訴外Kを個人的に嫌って訴外Kとの協業を困難であるとして我を通そうとし続けた,④被告はそのような原告のいわば我が儘にも耳を傾けて可能な限りの対応に努力してきたもので,被告に不法行為或いは債務不履行の事実はない,と。
しかし,被告が描こうとしたところは客観的裏付けを欠いた虚構であって,真相は,以下のとおりである。
(4)すなわち,①訴外Kは社内ではもちろん顧客との間でも多数のトラブルを生じさせており,被告としては,顧客に対するサービスを正常に提供するためには訴外Kをインストールサポート業務の唯一の担当者としておくことはできなかった,②そこで被告は,すでに実証済みの原告の力が不可欠であったことから原告を採用した,③しかし,訴外Kは原告再入社後も業務を正常に遂行することができなかったばかりか,原告による業務遂行の障害となり続けた,④被告としては,客観的にはこうした現状への対処を迫られていたが,対応方を誤れば訴外Kからどのようなリアクションがあるかも知れず,対処しかねた,⑤これに対し,原告は具体的事実を挙げつつ訴外Kの問題点を正面から被告に指摘したところ,その指摘は本来であれば被告がとるべき改善策(少 なくとも原告による業務遂行のための環境改善=訴外Kまたは原告の他部署への異動)を示すものであった,⑥ところが,被告は,原告からパワーハラスメント を受けた旨の訴外Kの申告があったことから訴外Kによるリアクションの怖れをいっそう強め,とるべき改善策をとらずに事態を放置し続けたばかりか,退職勧奨の末に原告の退職を実現させた。
このような実際の経過は,被告による原告に対する雇用契約上の使用者としての債務不履行乃至不法行為に該当するもので,被告は原告に対し,これにより原告が被った損害を賠償すべき義務を免れない。
以下,これらに関する事実及び時間外労働をめぐる被告の違法行為に関する事実ついて,証拠調べの結果を踏まえて詳述する。
(5)なお,原告がこれまでに提出してきた書面のうち,平成25(2013)年10月29日付「甲号証説明書(2)」の甲25の11についての立証趣旨欄に「2011年9月7日に原告がインストールサポートの体制についてR人事部長に対し面談を申し入れ,同日,面談が行われたこと等を立証する。」と記載したが,実際には面談は原告から申し入れたものではなくR人事部長が原告に対して申し入れたものであるので(原告尋問調書72頁),その旨訂正する。
第1 原告再入社前からの訴外Kの問題点
1 被告の主張・立証は客観的事実に反する
被告によれば,訴外Kは「業務に必要な限度では十分にコミュニケーションがとれていたし,顧客との電話対応も問題は無かった」「これら等の点から,業務遂行上の問題はなかった」(乙10・M陳述書),或いは「訴外K氏のコミュニケーション能力についても,業務上支障はなかったものと認識」(乙11・Y陳述書)とされ,O証人もこれに沿う供述を行った。
しかし,訴外Kの業務遂行状況に問題がなかったのであれば,つぎに挙げる数多くの客観的証拠に示されるとおり,被告従業員ら及び顧客らから多数の苦情が寄せられることはあり得ない。
実際には,以下のとおり顧客ら及び技術部のエンジニアをはじめとする被告従業員らとの間でトラブルが頻発するなど,被告の業務に大きな支障を生じさせていたことが明らかとなっている。
2 訴外Kについて数多くの苦情等があった事実(1) 訴外Kは,平成20(2008)年4月に入社してインストールサポート業務の専従者となったが,以下の各証拠が示すとおり,しばらくすると,顧客から早急 な対応が求められている問い合わせであるにもかかわらず対応を放置し,あるいは在席していても電話に出ないなどの問題を起こすようになった。
このため,顧客からの問い合わせは,当該顧客の営業担当者や技術部・情報システム部等の他部署に振り向けられるようになり,技術部のエンジニアたちは,インストールサポート業務をバックアップしていた情報システム部だけに頼るのではなく,本来の業務外であるにもかかわらずインストールサポート業務を開始する ようなったが,訴外Kは,こうした自身の業務遂行状態が知られることを阻むために,都合の悪いメールを削除し記録を残さないようにするなどして顧客の苦情に発展したケースを隠そうと試みるなどし続けた。
しかし,訴外Kの怠業は随所に深刻な影響を及ぼし,これを隠そうとする訴外Kの試みは成功しなかったことが明らかとなっている。
(2)例えば,訴外Kがインストールサポート業務の専従者となってわずか2か月後の平成20(2008)年6月には,技術部のエンジニアの中には,訴外Kの対応を期待することはできないとして業務範囲外のインストールサポート業務を自ら行う者がすでに現れるようになり(甲46,なお甲46の信用性については後述7頁),やがて技術部の何人ものエンジニアたちが同様に自らインストールサポート業務を行うようになった(甲20の13,46,74,75)。
また,訴外Kは,翌平成21(2009)年7月からは,大量のFAQを作成し始め,技術部のテクニカルアドミニストレーター(以下「技術部アドミ」ともいう)にも負荷をかけ始めたが(甲56),こうして訴外Kが作成したFAQのなかには他人が作成したものを自分で作成したもののように装ったものがあることも,顧客からの指摘を契機に判明しているところである(甲57)。
さらに,同年10月には,営業担当が顧客から受けた技術的な問い合わせを訴外Kに回したところ,これに回答するのが自身の担当業務であるにもかかわらず回答を拒否したため,困惑した営業担当が技術部の訴外Zに助けを求めるにいたった。これを受けた訴外Zが訴外Kに対応するよう促したところ,またしても訴外Kが対応を拒否したため,訴外ZはM部長に対し事実経過を報告しつつ訴外Kの「非協力的な態度に怒り心頭です。」とその心情を露わにしていたところである(甲16)。
また,この頃,訴外Kは,著作権のある製品パッケージ写真や劣化した画像をそのままFAQサイトに掲載しようとしており,これに気付いた技術部アドミが適切な画像との差替えを行うなど,訴外Kの無責任な業務遂行ぶりは他の従業員らの共通する認識となっていた(甲48)。
翌平成22(2010)年1月頃にも,訴外Kは,技術部アドミに対してFAQに関して独自に作成した身勝手なルールを要求し,たびたび口論となった。訴外Kは,顧客のためではなく自己満足のための「作品」と称する無駄な,しかも誤記を含むFAQ作りに執着し続け,「身勝手なK劇場のサイトばかりを作るのはどうかと思う」とまで評されていたのである(甲46)。その結果,顧客からも「FAQを増やせばいいというものではありません。考え方を変えて根本的な解決をしていただきたい。」「自己満足ページではなく,相手に分かってもらえるページの構成にしてください。」との苦情が寄せられた(甲47)。
しかし,訴外Kは,本来の業務であるマニュアル作成も行わず自己の態度を改めようとはまったくしなかった(甲16,46~48,56,57)。
(3)こうした原告再入社前からの訴外Kの業務遂行の実態については,原告の再入社直後である平成22(2010)年10月5日に,多くの被告従業員らが原告に対しリアルに述べているところである(甲46の1枚目及び3枚目下部)。
たとえば,訴外Wは「彼に仕事をお願いしても何も解決しない(いつまでもやらない)。完全に信頼関係は切れている。」と述べ,訴外Bは「いくら言ってもやらない。間違ったサポートや放置をするから信用できない。彼に頼むなら自分でやったほうがまし。」と述べ,技術部アドミらは「FAQの大作を大量に作られても,技術部のルールではなく,勝手な独自ルールで意味もない作業ばかり要求してくる。会社として身勝手なK劇場のサイトばかりを作るのはどうかと思う」「技術部のサポートルールを全く守らない。何度言っても同じことのくり返しで言うだけ無駄」と述べ,訴外Iは「全くやらないでただITに投げるだけ。結局技術部や営業部からのトラブルはITがやることになっている」と述べ,訴外Zも「かなり長い間面倒見て教えたけど,結局おぼえない。何度も同じことを聞いてくる。しまいには具合わるい,わすれたとか,いいのがれをする。」と述べるなど,訴外Kは無責任な業務ぶりから信頼できないことを全員が揃って述べていたところである。なお,被告は甲46の信用性を争うようであるが,上記の部分をはじめとする各記載がすでに挙げてきた数々の客観資料の記載とも合致していることによって,その信用性は十分に裏付けられているところである。
(4)また,原告再入社前からの訴外Kの無責任な業務遂行ぶりを示す客観的な資料のひとつであるFAQアンケート(甲47)について,被告は,「甲47における顧客の指摘は必ずしも訴外Kが作成したものを対象としたものではない」(被告第1準備書面10頁)と主張し,これが訴外Kに対する苦情であることを否定しようと試みた。
しかし,被告は,原告が「甲47で顧客から指摘されている件が訴外K作成したものについてであることは,被告においても当然に確認しているはず」(「準備書面(2)」11頁)と指摘して被告主張の根拠資料を示すよう求めたところ,被告は,その後提出した陳述書(乙9~11)においても「当時しかるべき主任者の決済を経たものがK氏の作成したFAQ」,「技術部としては,特段作成業務に問題はなかったものと判断」などと述べるのみで,根拠資料を示すことはなかった。
実際には,技術部アドミが管理していた「FAQ管理票」(甲54)に示されているとおり,顧客からの苦情対象のFAQ4件 (SY00216,SY00218,SY00276,SY277)(甲47),「見るだけ無駄」との苦情対象(SY00279)(甲55の1・2)を含む 平成21(2009)年1月以降分の約270件のFAQは,いずれも訴外Kが作成したものである。
さらに,当時,訴外Kが作成したFAQの内容確認と修正はバックアップを行っていた情報システム部(主にI氏)が行い,公開するための最終的判断と承認はY部長が行っていたが(甲54の3~5頁の備考欄),主に管理していた技術部アドミや承認を行っていたY部長は,訴外KがFAQを修正せずに放置し(甲56),他の者のFAQを勝手にコピーするなど(甲57),自己満足的なFAQを大量に作成してきたために,オリジナル優先あるいはFAQ整理などで対応せざるを得なかった(甲46,48,49)。
以上のFAQに関する実態は,後述のとおり原告再入社後にも共通するものであった。
(5)以上の立証済みの事実が示すとおり,原告再入社の平成22(2010)年10月1日時点では,訴外Kに対する技術部のエンジニアをはじめとする被告従業員らの信頼は崩れ去っていたのであり,これに反する被告提出の各陳述書(乙9~11)の記述及び訴外Oの証言は,これらの事実を大きく歪めるものである。
3 改善は被告にとっての喫緊の課題
(1) 被告の技術部長である訴外Yが「当社のサポートサービスはソフトウェアの販売と不可分に結びついており,当社としてはこのサポートサービスの充実を極めて 重視しております。」(甲51)と述べているとおり,被告にとってインストールサポートのサービスを顧客に対し正常に提供することは極めて重要であった。
しかし,上に見たとおり,技術部のエンジニアたちは担当顧客についてのインストールサポートは訴外Kには回さずに自らが行うという状況にまで至っていた。 こうした状況の下で,被告がきわめて重視していた顧客に対するサービスを正常に提供するためには,訴外K一人がインストールサポートの専任担当という状態を一刻も放置しおくことはできないというのが客観的な状況であった。
(2)これに対し,被告は,訴外Kは平成20(2008)年4月に被 告に採用されたが,社内でのコミュニケーションのうえで多少は問題があったものの,半年間の研修及び技術部によるバックアップもあったこと等から顧客対応 及び通常処理にはとくに支障は無かった要に描こうとするが(乙9~11),実際は以上の事実が示すとおりであった。
なお,M陳述書(乙10)に よれば,インストールサポート業務は組織再編により情報システム部から技術部に移管された旨が述べられているところ,その時期については明示されていな い。実際にインストールサポート業務自体が技術部に移管されたのは,原告再入社後の平成22(2010)年11月1日であり(甲52の1・2),この間, 訴外Kが担当者とされていたインストールサポート業務は,「KさんのバックアップとしてのIさんの業務,およびIさんが行っている他のライセンス・インス トールサポート業務等」(甲52の2)とあるとおり,情報システム部の訴外Iの全面的なバックアップを受けていたのが事実である。
また,被告によれば,訴外Kは入社後約半年間をインストールサポート業務習得のためにIT部門の座席で過ごしたが業務状況は良好で概ね9割程度のインストールサポート業務を担当できるようになったものともされる(被告「第1準備書面」10頁)。
しかし,実際には,訴外Kは上記のとおり訴外Iの全面的なバックアップを受けるとともに技術部のエンジニアらが担当業務外のインストールサポート業務を自ら行っていたのが事実であり(甲74,75),しかも,訴外Kが行うことが出来たのは,M陳述書(乙10)にいう「典型的かつ難易度が低い問題」に限られ,これについても同陳述書の作成名義人である訴外Mが原告に対し知らせているとおり(甲60),過去に原告が作成したドキュメント等を改定することもなくこれを頼りに行っていたに過ぎないのである。
(3)一方,被告は,遅くとも,訴外Kの採用からわずか9か月後である平成 21(2009)年1月時点で,インストールサポートを含む職種について経験者の募集(被告において経験者の募集が通常であることにつき,被告技術部長で ある訴外Yが閲覧等制限申立について提出した陳述書=甲51)を行っているが,これは,被告においても,以上に見てきたとおり訴外Kにインストールサポー ト業務をこれ以上任せておくことはできない状態にあったことから,他に経験者を採用して配置することが必要であったこと認識していたことを示すものであ る。
第2 原告再入社に至る経過
1 被告の主張・立証は客観的事実に反する
被告は,原告を再入社させるに際して事前に原告に対し訴外Kのコミュニケーション能力にやや問題があること等を説明し原告の了解を得ていたとするが,全く事実に反する。
すなわち,訴外Oの陳述書(乙9)における記述及び証言によれば,サポート業務は原告の再入社前は訴外Kが一人で担当していたがその業務量は 1.2~1.5人分程度あった,訴外Kにはコミュニケーションに若干問題があったので社交的な人物を採用して組ませることによりコミュニケーション能力の 向上を図ろうと考えた,訴外王は原告を直接知らずその技術力等についても知らなかったが再入社を希望していることを偶然知ったので接触することとし,採用 の具体化に当たっては原告に対し訴外Kとのコミュニケーションに問題がないかを事前に確認した,とされる。
しかし,訴外Oの述べるところは,他の点と同様に上記の点についても以下に述べるとおり事実を大きく歪めたものである。
2 原告の採用はかつての勤務からその実力を評価・期待してのもの
(1)第1に,原告の採用は,かつての勤務のなかですでに実証済みの原告の技術力が当時の被告にとって不可欠であったことからというのが真相であり,この点に関する被告の主張及び訴外Oが述べるところはいずれも事実に反する。
すなわち,原告は,平成19(2007)年5月に被告の前身であるフルーエント・アジアパシフィック株式会社を退職した後も訴外M部長をはじめとする複数 の同僚と交流があったところ,同年12月18日,訴外Mからのメール(甲58)で,旧CS(報システム部)の同僚1名が退職したことを知らされるとともに 「本気モードで,Nさんを再採用してはどうかという話も今は出ていたりします」との連絡を受けた。
さらに,翌平成20(2008)年1月18日にも
「後任??一人も履歴書きません(-_-;),Nさんくらいのスペックの人が欲しいのですが,なかなか難しいみたいです(*^_^*)仕事に窮屈したら,まだポジション開いているので大歓迎です。」
との連絡(甲59-1)があったことから,原告は手術を控えていたためすぐに動くことはできなかったが,参考までにSE(システムエンジニア)兼解析技術者が可能かどうか,また再就職に対する被告の状況を確認したところ,訴外Mの返事は
「出戻りは,全然OKですよ。覚えているか?わかりませんが,Sさんというひとが技術部にいるのですが,その方は出戻りです。興味があったら,連絡ください。いまだに強力に募集中です」というものであった(甲59の2)。
また,原告は,同年7月4日にM部長から
「N さんが会社に残していった各種のドキュメントやファイルは,今だに改訂されずに使われています。というか,今の担当の男の子(っていうか,俺よりか年上だ けど)は,Nさんのドキュメントだけが頼りでやっているみたいです。……Nさんの偉大さを思い知っていると思います。I君も最近は,成長してやっとこ さ,0.8人前くらい(2006年7月入社)になってきました」。
とのメール(甲60)を受けて専任者が決まったことを知ったが,ここに言う「担当の男の子」が訴外Kのことであることは,この当時には知らなかった(原告尋問調書20頁)。
そ の後,原告は,インストールサポートが機能していない状況を知らされるとともに他の同僚らからも機会があれば戻ってきてい欲しいとの誘いもあったことか ら,翌平成21(2009)年1月13日,経験があった「インストールサポート」を被告Webサイト上で選択して応募した。その結果,翌日には訴外Oから 電話があり再入社を強く勧められ,原告は電話でのやりとり後のメール(甲61・62)では「解析エンジニア」を希望する旨を回答していたが,結局のとこ ろ,被告は,M部長も上記のとおり高く評価していた原告を,前述した状況から是非とも必要としていたインストールサポート業務の担当として採用したのであ る。
(2)第2に,訴外Oが原告のことを直接は知らず,上記のように高く評価されていた原告の技術力についても知らなかったというのも,凡そ事実に反する。
原 告は,被告の前身であるフルーエント・アジアパシフィック株式会社において平成18(2006)年1月から翌平成19(2007)年5月までインストール サポート業務に従事していた経験があったが,訴外Oは,平成18(2006)年2月20日に行われた「GL会議」(被告技術部のグループリーダー= 「GL」を週1回集めて行われる会議)において,研修終了後の原告をその技術力を踏まえて技術部に配属してサポート業務を担当させるよう要望していた(甲 77)。
そして,現実にも原告はサポート業務を担当することとなったものであって,その後も,訴外Oは訴外M及び技術部員らとのやりとりのなかで原告の配置・職遂行状況等に言及しているところである(甲78・79)。
以上に反して,原告のことをその技術力を含めて直接知らなかったとする訴外Oの証言は,全くの虚偽である。
(3)第3に,再入社の具体化に当たって訴外Oは原告に対し訴外Kとのコミュニケーションに問題がないかを確認した,との点も事実に反する。
前 述したとおり,原告によるWeb上での応募の直後に訴外Oから原告に連絡があったが,この間に訴外Oが原告に確認を求めたのは「転職の意思確認」であって 「コミュニケーションの問題」その他訴外Kに関する話は全くなく,メールのやり取りの中にも訴外Kに関する記載は一切ない。
また,訴外Oは原告 に対し,平成21(2009)年10月20日に「NさんがAJKに戻る気持ちは現在ありますか」(甲63)との問い合わせを行い,翌平成22(2010) 年5月7日にも「Nさんの現在の意思(ANSYSJAPANに転職の意思)を確認したく」(甲64)との連絡を行っていたが,そのいずれにおいても訴外Kについての言及はない。原告は,この2回目の連絡により同年5月11日及び同月31日の面接に至ったものの,面接結果の連絡がなかったために同年7月8日に「また違う機会で一緒にお仕事できることも可能かと思います」と辞退した(甲9の2頁)。ところが,その直後に,訴外Oは「一言言いますと全くの誤解で す……今日午前も,別件を早く片付け,Nさんの採用を進めたいと人事とはなしました。」(甲65)とすぐに返事を寄越しているが,これらの経過及びその後 の再入社決定にいたる如何なる経過のなかでも,訴外Kのコミュニケーション能力等に関する言及あるいは「訴外K氏とうまくやって行ける人」などという採用条件は出されなかったのである(実際の採用条件は,甲9の2頁のとおり「一度辞めた社員なので1年間は正社員ではなく契約社員でなければならない」というものであった)。
第3 原告再入社後の実態と被告の対応
1 訴外Kの業務遂行上の問題
訴外Kの無責任きわまる対応は平成22(2010)年10月1日の原告の再入社後も変わらなかった。
インストールサポート業務は正規従業員である訴外Kと雇用期間1年の非正規従業員であった原告の二人体制で行うこととされたにもかかわらず,訴外Kは業務を 正常に遂行することができなかったばかりか,原告をはじめとする他の従業員らの業務遂行の障害となり続け,早くも同年11月には,実際上は原告がその大半 を処理しなければならないことが明らかとなった(甲17の2~4)。
また,訴外Kは,従来からFAQ作成について起こしていた問題を原告再入社後においても繰り返して他部署にも迷惑をかけ続けており(甲48・49),これについての善後策も原告が再入社直後から取らなければならないこととなった。
すなわち,前述(7~8頁)したFAQ公開のための最終的判断と承認は原告の再入社後しばらくの間もY部長が行っていたが,訴外Kが「作品集」などと述べ るので迂闊には対応できない状況であったため,同年10月15日,原告とY部長との打合せで,旧FAQチームの関係者との間で問題点について話し合った結 果を踏まえて「インストール関連のFAQだけがまだ整理されていない。」ことを確認のうえ,まずは内容チェック,誤記修正,重複ページの整理を行い,そのうえでカテゴリ分けによる再整理を行うこととなり(甲46の2頁下部),3年以上放置されてきたシステム関連のFAQページを原告が整理することとなったのである。
2 原告の訴外Oに対する報告・要請と訴外Oの対応等
これを受けて,同月21日,訴外Oは原告及び訴外Kに対し「案を作って話します」と連絡していたが,にもかかわらず,訴外Kは訴外Oに対する返信で原告に相談なく自己に都合のよい案を示したことから,訴外Oは「Nさんと話してまとめた案ですが」と驚きを示した(甲53の1)。原告は訴外Oに対し,同年11月14日には,このままでは二人体制の意味がないのでどのようにしたらよいか検討するよう求めた(甲17の1・2)。(2)ところが訴外Oは,訴外Kの業務態度の改善に向けて具体的な方策を採らないままに,同月17日,原告に対し,訴外Kとの二人体制のなかで原告がチームリーダーとして訴外Kのマネジメントを行うよう命じた。
雇用期間1年の非正規従業員であり再入社から1か月余りにとどまる原告に対し,すでに3年近くの実務経験を有している正規従業員である訴外Kのマネジメントを命じることの不合理は明らかであった。
なお,訴外Oは,原告をチームリーダーとしたのは原告自身の要望にもとづくかのように述べるが,この11月17日の原告・訴外O及び訴外Kの三者のやりとりは原告の打合せノート(甲53の4)の記載のとおりであって,原告の要望にもとづくなどというものではなく,また,そのさいに訴外Kは「命令するな」と大声を出して反発していたところである(原告尋問調書21~22頁)。
こうした訴外Kの態度はこのときばかりではなく,顧客からのサポート依頼の分担を原告が訴外Kに対して伝えようとしても,訴外Kは理由なく分担を拒否するばかりであった。その訴外Kの対応も,当初は原告が口頭で行っていたところ拒否されたことからペーパーで伝えようとしてもこれを破り捨てあるいは目の前でシュレッダーにかけることすらあったため,原告は,訴外OをC.C.に入れたメールで行うよう変更せざるを得なかったほどである(前同24頁)。
こうしたことから,原告は訴外Oに対し,同年12月5日には原告の努力には限界がある旨を訴えていたところでもある(甲20の4)。(3)また,原告は訴外Oに対し,平成22(2010)年11月以降,原告と訴外Kそれぞれのシステムサポート業務の処理状況を毎月集計して報告しつつ,原告に過重な業務負担が強いられ続けていることを訴え続けたが,この報告は平成24(2012)年3月分まで続けられた(甲19の1~13)。これに加えて,原告は訴外Oに対し,原告及び訴外KそれぞれのANSYS製品・ANSOFT製品についてのサポート依頼についての処理状況,Siebel米国へのサポート依頼についての処理状況の詳細についても報告し続けた(甲22の1~3,23の1~3)。
こうした定例報告に加えて,原告は訴外Oに対し,訴外Kの業務遂行上の具体的な問題点についての実情を以下のとおり再三に亘って報告しつつ事態の改善のために部長としての権限を行使するよう求め続けた。
すなわち,平成23(2011)年3月29日には,訴外Kが社内各部署からのサポート要請に応じることを拒否している実態を数々の事例ごとに具体的に指摘 しつつ,訴外Kが原告の指摘にはまったく耳を貸さず業務拒否を続けているため協業を続けることは無理と思われることなどの実情を訴えた(甲18の1)。し かし,訴外Oがなんら対応しなかったことから,原告は訴外Oに対し,訴外Kの指導は原告には無理であること等を再度訴えた(甲20の7)。
同年 4月3日には,原告は,技術部の各グループリーダーらに対しても,訴外Kの業務態度を改善させることは無理であり,訴外Kに任せられない分の業務は原告自 身が行わざるを得ない状況が続いていることなどの実情を伝え,事態の打開をはかるべく訴外Oに働き掛けるなどの協力を得たい旨を訴えた(甲35)。(4) その後も,原告の訴外Oに対する実情を具体的に示しての訴えは,同年4月11日(甲18の4),同月22日(甲18の2),5月9日(甲18の3),6月 25日(甲20の10)同月27日(甲20の8),7月4日~8月5日(甲20の9),8月13日(甲20の11)等々,多数回にのぼる。しかし,訴外O は,原告が実情を具体的に報告しつつ改善策をとるよう繰り返し求め続けたにもかかわらず事態を放置し続け,このため訴外Kが担当業務を放棄し続けるなど,状況は改善されないどころか却って悪化して行ったのである。
被告としては客観的にはこうした現状への対処を迫られていたが,前述した平成 22(2010)年11月17日の訴外O及び原告を前にした大声を張り上げての反発をはじめとする訴外Kの日常的な態度から,対応方を誤れば訴外Kからどのようなリアクションがあるかも知れず対処しかねていたというのが真相である。
第4 訴外Kによるいわゆる「パワーハラスメント」の訴えと被告の対応
(1)原告は,平成23(2011)年8月18日,技術部のマネージャーを含む全員をC.C.に加えた訴外K宛のメールで,原告が営業担当からの直接の依頼を受 けて対応中の顧客に突如として訴外Kが割り込んだことについて「本件ですが,営業Cさんから直接自分宛てにサポート依頼がきたものです。お客様から電話も きていないのに,勝手に人がサポート中の案件に手を出さないでください。申し訳ありませんがお客様に迷惑をかけるサポートならやっていただかなくて結構で す。」と訴外Kに抗議した(甲25の5)。これに対し,訴外Kは,原告を逆恨みしてか,その後は担当業務を全く行わずに10日間余りを経た同月末日乃至同年9月初め頃,原告からパワーハラスメントを受けているなどと虚偽の事実を訴外O及び被告コンプライアンス機関に訴え出た(甲26の1・2)。
なお,被告は,上記の経過について,「原告の訴外Kに対する仕打ち」と称しつつ,あたかも原告が訴外Kに対する理由のない非難を必要もなく多くの関係者に対し送信した旨を主張するが(被告「第1準備書面」11頁末以下),このような被告の主張が凡そ事実を無視したものであることについては,既に原告「準備書面(1)」16~21頁において数多くの客観的証拠に基づきつつ詳細に反論したところであるので繰り返さない。
(2)訴外Kの上記訴えを受けて同年9月2日,訴外Oは,原告をROOM7に呼び出して聴取を行い,訴外Kの訴えが認められれば原告は即時解雇となる旨を申し伝えた(訴外Oはこれを否定するが,原告が当時の明確な記憶にもとづいて作成した甲8の24丁,甲9の7頁の記載等のとおりである。)。また,同月7日には訴外O及びR人事部長による原告に対する事情聴取が行われ,そのさいに原告は,持参した資料にもとづきながら,前述した訴外Kの業務遂行の具体的状況についての数々の事実を説明し,訴外Kによる訴えにはまったく理由がないことを明らかにした。これに対してR人事部長は「こんな状況になるまで誰も報告しなかったのか」と驚きを示すなどしたが(甲8の24丁,甲9の8頁),被告は,実情を訴えて「このままでは退職するしかない」として部署移動を希望した原告に対し,後述のとおり引き続き訴外Kとの協業を命じ続けたのである。
また,これらと並行して同月2日から7日にかけて人事部による技術部所属従業員らからの聴取が行われるとともに,原告が使用していたパソコンも調べられたが,訴外Kの勤務態度やこれまでのトラブルが周知の事実であって訴外Kの訴えは退けられる結果となったのである。ちなみに,原告が 退職手続のさいにこの件について触れたことに対し,訴外Oも「それさあ,人事がさあ,それ晴れたんじゃあないですか(笑)」と述べているところである(甲42,下から8行目)。
2 事実を歪める被告主張
被告は,先に触れた「原告の訴外Kに対する仕打ち」との主張に加えて,原告が訴外Zとの間でやりとりしていた同年8月22日及び23日のメール(乙5,6)を提出するとともに証拠説明書においてそれらの立証趣旨を,前者については「原告が訴外Kを無視し,業務から外そうとする意図を持っていたことを証明する。」,後者については「原告が,訴外Kのパソコンに不正にアクセスし,内容を確認していたことを証明する。」としている。
しかし,8月22日のメール(乙5)について言えば,すでにこの時点までに原告から訴外Oに対し訴外Kの問題点を具体的に指摘して対処を求め続けてきたにもかかわらず訴外Oが対応しなかったことから,原告が訴外Zを含む技術部員らにも相談していたところ,訴外Zから,訴外Kに対してはサポートその他の仕事も回さない方が得策である旨の助言を受けていたことから,この助言どおりにする他になさそうである旨を率直に述べたものであって(原告尋問31頁),このような認識は,原告及び訴外Zのみでなく多くの被告従業員らに共通するところでもある。
また,8月23日のメール(乙6)について言えば,そもそも訴外Kが原告をはじめとする他の従業員らのパソコンの内容を日常的に監視していたという実情のもとで(同83頁),原告が訴外Kのパソコンの内容を見たか らと言ってこれを非難することも的外れである。しかも,原告がKのパソコンに「不正にアクセス」していたというのであれば,そのことは前記の原告が使用し ていたパソコンについての調査の中ですでに判明していた筈であって,その結果,原告は少なくとも何らかの処分は受けていたはずであるが,実際には,原告は何らの処分も受けていないのである。
3 訴外Kによる訴えの客観的な効果
こうして,訴外Kの訴えた原告による「パワーハラスメント」なる事実は,被告も結局は認めることはなかったが,逆に,被告にとっては,訴外Kが今後ともどのような理不尽な行動に出るかについて警戒心をいっそう高める結果となったのである。
こうして,被告は訴外Kのリアクションを怖れてその後も問題を放置し続けた。
第5 原告退職に至る経過
1 いわゆる「暫定措置」について
訴外Kによる原告についてのパワハラ疑惑の訴えを受けた人事部の調査の後も,インストールサポート業務を原告と訴外Kの二人で担当して行うという業務体制の基本は変更されず,わずかに,平成23(2011)年10月1日からはサポート依頼のあった製品別に原告と訴外Kとを担当を分けるという「暫定措置」が開始され,これが同年12月まで続けられさらには翌年3月まで延長されることとなった(甲25の13,原告尋問調書33~34頁)。
原告は,訴外Kによる新たなる虚偽報告や報復など身の危険と恐怖を感じながら出社する日々が続いたため,訴外Oに対し,訴外Kとの協業は無理を強いるものであって再発防止のための配置転換も必要であること,いつまでも強要し続けること自体が原告に対するパワーハラスメントであり何の対策もなければ結局は自分が退職するしかない旨を何度も訴え続けたが,にもかかわらず訴外Oは,このような「暫定措置」を一方的に決定・発表したのである。
この「暫定措置」を発表した訴外Oのメール(甲25の13)では,原告と訴外Kとの調整相談役を訴外Tが担当する旨が述べられているが,実際には,訴外Tがなんらかの調整を行った事実はなかった(原告尋問調書34~35頁)。
なお,被告は,この「暫定措置」は原告の求めに応じて行われたものであると主張するが事実に反する。
すなわち,原告についてのパワハラ疑惑は人事部の調査の結果晴らされたが,この調査のなかでR人事部長は原告に対し,訴外Kとの協業は二度とさせないと述べており(甲8の24丁,甲9の8頁),また,原告だけでなく訴外Kも配置転換を要望していた(甲26の1・2)。ところが,このR人事部長の言は全て覆され,1か月足らず後の同年10月1日からの「暫定措置」が訴外Oによって発表されたのであり,このような「暫定措置」は原告の求めに応じたものなどではなかった。
また,訴外Oは前記の「暫定措置」を発表した訴外Oのメール(甲25の13)で「Oが最終責任を持ちます」と述べながら,実際には何らの責任もとらなかったばかりか,つぎのとおり原告に退職を迫りつつこれを実現させたのである。
2 その後の被告の対応について
上記の「暫定措置」の内容は,翌平成24(2012)年1月からは,サポートは訴外Kが担当し,原告は暫定的に新製品のマニュアル作成を担当するというものとなったものの,原告は訴外Kが担当するサポートについての顧客からの苦情処理に追われる結果となった(原告尋問調書35~37頁)。
さらに,同年3月6日,訴外Oによって,サポート依頼のあった製品別に再び原告と訴外Kとで担当を分けること,原告不在のさいのバックアップを訴外Kが行うこととする業務分担を同月12日から実施する旨が全従業員らに対し発表された(甲30)。この新たな業務分担は,「当分はメインサポートをNが行う」とあるとおり一時的な筈であったが,実際には「当分」にとどまるものとはならなかった。しかも,このような製品別の分担は,実際には原告の負担解消には程遠いものであるとともに,訴外Kの無責任な対応をますます助長させるものとなった。
すなわち,この業務分担は,原告と訴外Kとで被告の主力製品の全てを分担するものであるところ,もともとの製品分担による業務量は訴外K3対原告7というものであったうえ(原告尋問調書38頁),原告には訴外Kのみによるバックアップという無意味な体制の一方で,訴外Kには訴外T(実際には単独ではなくG4の旧アンソフトグループ)によるバックアップ体制という手厚いものであった(甲30)。
しかも,実際には,訴外Kが担当する製品についての相談が原告に回ってくる,さらには,訴外Kの無責任な対応に対する顧客からの苦情に対する対応依頼が相次いで原告に寄せられるなどの事態となったこと(甲28の2~4)等の詳細は,すでに原告「準備書面(2)」(26~27頁)において,証拠にもとづく具体的事実を挙げて指摘したとおりである。また,訴外Kは,原告不在時のバックアップを行うこととされたにも関わらず,システムサポート宛のメールの全てについて受信拒否まで行ったのである(甲31の4)。
こうして,原告は,その要望を悉く無視され,インストールサポート業務を訴外Kと原告とで行うという体制の問題点はついに解消されないまま,日々恐怖に耐え続けることを強いられた挙げ句に,退職を選択せざるを得ない状態に追い込まれたのである。
3 被告の配慮なるものについて
(1)被告は,「訴外O自身も,原告と訴外Kの関係を取り持つため,3名で食事を行ったり,個別に話し合ったりして原告と訴外Kの間のコミュニケーションを図るように努めていた。」とも主張し,訴外Oはこれに沿う旨を述べるが,原告は訴外Kを含め3名で食事したことなどは一切ない。
(2)また,被告は,座席の移動についても配慮した旨を主張するが,座席移動の実際の経緯は,つぎのとおりであった。
すなわち,原告は平成23(2011)年9月3日に訴外Kの隣の席(乙8の1)から一つ間を置いた席(乙8の2)に移動したが,原告は体格も原告とは大きく異なり男性である訴外Kの異常な行動からすでにこのときまでに身の危険を感じて周囲に助けを求めており(甲9の6頁下段),同月2日の訴外O宛のメール(甲25の10・1枚目最下段以降)で願い出て移動したものである。ところが,訴外Oは,同年11月24日,このようにして危機を感じて移動していた原告の席を,再び訴外Kの席と隣接させることを原告及び訴外Kに知らせたのである(甲25の17)。
なお,原告は,翌平成24(2012)年2月24日(金)夕方には,一つ間を置いた席(乙8の2)からさらに離れた席(乙8の3)に移動しているところ(甲8の33丁),被告は,これを「被告の承諾を得ずに勝手に原告がその判断で行った」とするが,これが事実でないことはすでに原告「準備書面(2)」(28頁)において詳細に指摘したとおりである。
(3)さらに,被告は,訴外Oが原告の異動にも努力したなどと述べるが,訴外Oが原告に対し異動を検討した旨を述べたことは,原告が訴外Oによる退職勧奨に応じるに至るまで一度もなかったのみならず,検討の結果を尋ねる原告に対しても,つぎに見るとおりあくまでも現状のまま勤務を続けるか退職するかと迫ったのである。
前述した訴外Kによる虚偽の「パワハラ」の訴えの後にも,同年10月から11月に技術部内でサポートとプリセールスに分ける話があったさいに原告も異動を願い出ていたが,システムサポートを原告と訴外Kに担当させ続けるとしてその実現を最後まで阻んだのは,他ならない訴外Oであった(甲9の10頁,甲8の50・52丁)。
しかも,訴外Oは,再入社以来の原告からの数々の具体的な事実の指摘を伴う異動についての切実な要望について,これを悉く無視し続けた挙げ句に,すでに精神的にも限界に達していた原告に対し,「他に選択肢ないよ。この会社を辞めるか」「嫌な中で,仕事だけやる。」(甲40)と,二者択一を迫るとともに,退職を申し出た原告に「もし面倒であればあれですよね。こういうメールに,昨日のメールに印刷したメールに僕が人事に話をして,人事に認めてもらうようにします」(甲42)などと,一切引き留めることもなく人事も介さず即日退職手続を進めようとしたのである。
なお,被告は,甲40等に記録された訴外Oの発言については「やや誤解を与えかねないものが見られる。」が,訴外Oは日本語を母国語とする者ではないため これを考慮すべき旨も主張する。しかし,訴外Oは,被告会社内で長年に亘って日本語で会話を続けており,先にも指摘した原告の再入社にいたる経過のなかで の「また違う機会で一緒にお仕事できることも可能かと思います」との婉曲表現による辞退の申出も,即座に理解して対応しているところである。
(4)こうして,被告は,訴外訴外Oによる原告に対する退職勧奨に応じた原告の退職を期待しこれを実現させたのである。
第6 労働基準法37条違反の債務不履行乃至不法行為
1 原告の時間外労働時間の実態と被告による割増賃金不払い
原告の時間外労働時間の実態は,原告が被告在職中に記録していた勤務状況ノート(甲8)の記載のとおりであり,被告が原告に対して本訴請求にかかる対象期間について時間外労働時間についての割増賃金をまったく支払ってこなかったことは争いがない。
なお,被告は甲8の記載の信用性を争いつつ原告の時間外労働時間の全てを否定してきたものの,訴外Oの証言(速記録40~41頁)によっても原告が時間外労働を行っていたこと自体は否定すべくもないところである。
2 被告の悪質性
(1)被告は,原告をはじめとする従業員らの実労働時間の把握がきわめて容易であるにもかかわらず,「勤之助」と呼ばれるシステムによる本人申告に委ねて自らはこれを把握してこなかった。
使用者が労働者の労働時間を適正に把握すべきであることは言うまでもないところであるが,厚労省労働基準局長・平成13年4月6日付け基発第339号「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」は,「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置」として,始業・終業時刻の確認及び記録の方法としては,使用者が自ら現認することにより確認し記録すること,またはタイムカード,ICカード等の客観的な記録を基礎として確認し記録することを原則としている。そして,この原則的な方法によらず,「自己申告により労働者の始業・終業時刻の確認及び記録を行う場合」には,「自己申告により把握した労働時間が実際の労働時間と合致しているか否かについて,必要に応じて実態調査を実施すること」その他の措置を講ずることを求めている。
ところが,被告は,上記「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」をも遵守せず,原告をはじめとする従業員らの労働時間の把握を,従業員らの自己申告による「勤之助」の記録に専ら委ね続けてきたのである。
(2)被告にとって,原告をはじめとする従業員らの時間外労働の実態を把握することは,困難どころかきわめて容易なことであった。
すなわち,「勤之助」上の記載にもかかわらず,原告ばかりでなく被告技術部所属の多数の従業員らが現に所定就業時間を超えて業務を行っていた実態は,訴外O 部長も現認していたところであるばかりか(O証言調書40頁),メールでの業務上のやり取りの記録をはじめとする数々の記録からも被告において十分に把握 し得ていたところである。
ところが,被告は,「勤之助」により申告された労働時間が実際と合致するか否かをなんらかの方法により検証する方策は一切採っておらず,原告の実際の労働時間についても,原告が使用していたパソコンのログイン・ログアウトの記録,原告の入退室記録などの客観的な記録によって把握し得たにもかかわらず,これらを一切行わなかった。
このように,被告は,「勤之助」システムによる自己申告にかかる労働時間が時間外労働の実態を反映していないことを知りながら,あくまでも「勤之助」上の記載のみによって労働時間管理を行い,原告をはじめとする従業員らに対する時間外割増賃金の不払いを続けてきたのであって,この被告の労働基準法違反は確信犯ともいうべき悪質なものである。
(3)そればかりか,被告は,本訴前に原告代理人から指摘を受けた後も,さらには本訴の中でも,原告の時間外労働の事実について全てをひたすら争い続けてきた。
すなわち,本訴提起に先立つ平成25(2013)年3月18日,原告代理人は被告に対し「通知書」(甲6の1)送付し,その中で,被告による原告の始業・終業時刻の適正な把握・記録が行われていれば在職中の原告の時間外労働の事実は容易に認められる筈であることを指摘していた。なお,使用者はその雇用する労働者の労働時間に関する記録について3年間の保管義務があるところ(労基法109条),本訴請求にかかる未払割増賃金は2011年2月分(同月1日から同月末)以降のものであり,この期間の原告に関する記録はこの時点でも上記保管義務の期間内のものであった。
また,同年4月19日,原告代理人は被告代理人嘉納弁護士に対し,「N氏の日々の出退勤時刻は,オフィスへの出入りにさいしてのカードキーの記録(あるいはパソコンのログイン・ログアウトの記録)等々により,会社側において十分に確認できる筈と存じます」と指摘していたところである(甲50=原告代理人作成の「報告書」)。
さらに,本訴提起後の同年7月4日,被告代理人嘉納弁護士は原告代理人に対し,原告が使用していたパソコンを分析した結果,原告がこのパソコンから被告会社のサーバーを介して訴外Kのパソコンにアクセスして内容を監視していたことが判明した旨を述べていた(甲50)。従って,嘉納弁護士が原告代理人に対して述べていたところが真実であれば,被告は原告の在職中におけるパソコンへのログイン・ログアウト時刻を少なくとも上記分析の時点で十分に把握できた筈である。
にもかかわらず,被告は,「勤之助」の記録のみを挙げて原告の時間外労働の事実を否定し,原告自身による労働時間等の事実を記載した甲8の信用性を争い続けるという不誠実極まる対応をその後も維持し続けて真実の隠蔽を図ろうとしたのである。
しかも,平成26(2014)年5月15日に実施され本訴の弁論準備期日において,原告代理人は,原告の時間外労働の実態はパソコンのログイン・ログアウト時刻,入退室記録などの客観的な記録によって把握し得た筈である旨を指摘したが,被告代理人石黒弁護士は,これらの記録は本訴提起前に双方代理人間で交渉を行っていた当時から既に存在しておらず,「勤之助」の記載の他には原告の労働時間を把握できる資料は当時も現在も存在しない旨を明言した。
この石黒弁護士が述べるところが事実ならば,被告は,前述の平成25(2013)年3月18日付の原告代理人の被告宛「通知書」(甲6の1),さらには同年4月19日の原告代理人の被告代理人に対する指摘(甲50)によって,原告の労働時間はパソコンのログイン・ログアウト時刻,入退室記録などの客観的な記録によって確認する必要を認識しながら,これらの客観的な記録を意図的に廃棄したということとなるのであって,被告の悪質性はきわめて大きい。
(4)なお,被告は,原告は「勤之助」システムによる自己申告にさいして自ら時間外労働を申告しなかった,或いは在職中に未払割増賃金の請求を行っていなかった旨を指摘する。しかし,原告は退職願いを提出した翌年1月に労基局に相談するまでは未払割増賃金の請求権があることを知らなかったのが事実であるうえに,仮に知っていながら在職中に請求していなかったという場合であっても,不法行為あるいは債務不履行が否定されることもない。
第7 結論
以上による原告の被害は少なくとも金400万円を下回らず,内金348万2032円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める原告の本訴請求は認容されるべきものである。
以上