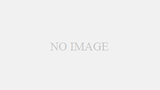平成27年3月27日判決言渡 同日判決原本領収 裁判所書記官
平成25年(ワ)第16709号 賃金等請求事件
口頭弁論終結日 平成27年3月6日
判 決
原 告
同 訴 訟 代 理 人 弁 護 士 志 村 新
東京都新宿区西新宿六丁目10番1号
被 告 ア ン シ ス ・ ジ ャ パ ン 株 式 会 社
同 代 表 取 締 役 大 古 俊 輔
同 訴 訟 代 理 人 弁 護 士 嘉 納 英 樹
同 訴 訟 復 代 理 人 弁 護 士 萢 宇 晟
主 文
1 被告は,原告に対し,50万円及びこれに対する平成25年2月7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,これを6分し,その1を被告の負担とし,その余を原告の負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
事 実 及 び 理 由
第1 請求
被告は,原告に対し,700万円及びうち348万2032円に対する平成2
5年2月7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
本件は,原告が,被告が原告との労働契約上の義務として負う安全配慮義務又
は労働者が労働しやすい職場環境を整える義務を怠った旨を主張し,被告に対し,
民法715条の不法行為責任又は同法415条の債務不履行責任に基づく損害賠
償(慰謝料)等を求める事案である。
1 前提事実(争いのない事実後掲証拠及び弁論の全趣旨による認定事実)
(1)当事者等(争いなし)
被告は,米国ANSYS Inc.の100%子会社として平成13年に設
立された日本法人が数社の買収を経て平成22年8月に設立した資本金100
0万円の株式会社であり,コンビュータのソフトウエアの開発・販売,コンビ
ュータのソフトウエアに関するマーケットリサーチ・保守サービス・コンサル
ティングその他の業務を目的とする。肩書地に東京本社を,大阪市内に大阪営
業所をそれぞれ置き,平成24年12月時点の従業員数は約140名である。
原告は,平成22年10月1日に被告に従業員として(当初は雇用期間を同
日から1年間とする従業員として,平成23年7月1日からは期間の定めのな
い従業員として)採用され被告の技術部に所属し「インストレーションサ
ポートエンジニア」の業務に従事していたが,平成25年2月6日付けで被告
を退職した。なお,原告は,平成18年1月1日から平成19年5月末日まで
被告の前身であるフルーエント・アジアパシフィック株式会社(以下「被告の
前身会社」という。)の正規従業員として在籍し,インストレーションサポー
トエンジニアの業務に従事していた。
(2)インストレーションサポートエンジニアについて
「インストレーションサポートエンジニア」とは,被告の前身会社で使用さ
れていた名称であり,原告及び被告聞の雇用契約書に記載された職務名である。
この職務に係る業務は,顧客のシステムを幅広く理解して問題解決・サポート
を早急に提供する業務で,コンビュータ業界でのシステムエンジニア及びカス
タマー担当の経験が要求されるとともに,顧客からの直接の問い合わせ窓口と
なることから,会社を代表する総合技術窓口も兼ねており,顧客のクレーム・
要望等に営業・技術部門と連携しつつ対処することが求められる(以下,イン
ストレーションサポートエンジニアに係る業務を「インストールサポート」と
いう。)。(争いなし)
(3)原告の被告入社後の状況
原告は,平成22年10月1日に被告に入社し,被告の技術部(以下単に「技
術部」という。)でインストールサポートに従事した。原告の入社以前は,平
成20年4月に被告に入社したK■■(以下「K」という。)がインスト
ールサポートを専任で担当していたが,原告の入社後は,インストールサポー
トの担当は原告及び、Kの二人体制とされた。
Kには,顧客及び技術部のエンジニアとの間でうまくコミュニケーション
がとれないこと等があったため,原告は,当時の技術部部長であり,原告の上
司であったO■(以下「O部長」という。)に対し,繰り返し,Kの状況を
報告しつつその改善を求めていた。(争いなし)
(4)Kによるパワーハラスメントの訴え
平成22年8月18日,原告がKに対し,技術部の全員を宛先に加えたメ
ール(甲25の5)で,Kの顧客に対する対応には問題があることを指摘し
て批判したところ,Kは,原告の上記行為がパワーハラスメント(以下「パ
ワハラ」という。)に当たる行為であり,原告がKの仕事を剥奪していると
してO部長等に訴え出た。これを受けて,平成22年9月,被告の人事部(以
下単に「人事部」という。)により技術部に所属する従業員らの聞き取り調査
が行われた。(争いなし)
(5)原告の退職
その後も,原告は,O部長に対し,Kと協同して業務を遂行することは不
可能であることなどを繰り返し訴えたが,平成24年12月26日,原告は,
O部長に対し,退職の意思を伝え,平成25年2月6日付けで被告を退職する
旨の退職届を被告人事部に提出した(争いなし)。
2 争点及びこれに対する当事者の主張
本件の争点は,債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償請求の可否である。
(1)原告の主張
ア 安全配慮義務違反等による不法行為又は債務不履行
職場において労働者に対し職務に関連して精神的又は身体的な苦痛を与え
ることにより心身の安全,行動の自由などの利益又は権利を侵害する行為は,
不法行為に該当し,その行為者は,当該労働者に対し,民法709条及び同
710条に基づく損害賠償責任を負い,当該行為者の使用者もまた民法71
5条に基づく損害賠償責任を負う。また,使用者は,雇用する労働者に対し,
労働契約上の義務として安全配慮義務を負っており(労働契約法5条),そ
の一環として労働者が労働しやすい職場環境を整える義務を負っていると
ころ,上記のような不法行為を放置することはこの義務に違反するものであ
るから,使用者は,故意又は過失の有無を問わず,これにより労働者が被っ
た損害を債務不履行(民法415条)に基づき賠償すべき責任を負う。
被告は,次のとおりO部長による原告に対する不法行為を放置したことに
つき,O部長の使用者として不法行為責任を負うとともに,原告の使用者と
しての債務不履行責任を負う。
(ア)原告が被告に入社するに至る経緯
原告が入社する以前から,Kは,顧客ら及び技術部のエンジニアを始
めとする被告従業員らとの間でトラブルを頻発させるなどしており,技術
部のエンジニアを始めとする被告従業員らの信頼関係は完全に崩れ,被告
の業務に大きな支障を生じさせていた。
そこで,被告としては,被告の前身会社で既に実証済みの原告の技術力
が被告にとって不可欠であったため,原告をインストールサポートの担当
者として採用したが,この際,被告から原告に対し,Kのコミュニケー
ション能力等に関して言及されることも,Kとうまくやっていける人な
どという採用条件を示されることもなかった。
(イ)原告入社後の実態と被告の対応
Kの無責任な対応は,原告の入社後も変わらず,平成22年11月に
は原告が業務の大半を処理しなければならない状況であったが,O部長は,
Kの業務態度の改善に向けた具体的な方策を採らないまま,原告に対し,
チームリーダーとしてKのマネジメントを行うよう命じた。
原告は,O部長に対し,原告及びKの各サポート業務の処理状況を毎
月集計して報告する(甲19のlないし19の13,甲22の1ないし2
2の3,甲23の1ないし23の3)ほか,Kの業務遂行上の具体的な
問題点について実情を再三報告し,原告に過重な業務負担が強いられ続け
ている状況を訴えて対応を求め続けたが,O部長は,事態を放置し続け,
状況はかえって悪化した。
(ウ)Kによるパワハラの訴えと被告の対応
Kが原告からパワハラを受けているなどと虚偽の事実をO部長及び
被告コンブライアンス機関に訴え出たが,人事部による調査の結果,K
の訴えは退けられた。原告は,O部長らに対し,実情を訴えて,「このま
までは退職するしかない。」として部署の異動を希望したが,O部長らは,
原告に対し,引き続きKとの協業を命じ続けた。
(エ)原告の退職に至る経緯
原告は,Kによる新たな虚偽報告や報復など身の危険と恐怖を感じな
がら出社する日が続いたため,O部長に対しKとの協業は無理を強い
るものであって再発防止のための配置転換が必要であること,何の対策も
なければ結局は原告が退職するしかない旨を何度も訴え続けたが,O部長
は,平成23年10月からはサポート依頼のあった製品別に原告とKの
担当を分けるという暫定措置を一方的に決定・発表し,平成24年3月か
らは,原告とKとで被告の主力製品の全てを原告7対K3の業務量で
分担するなどの不均衡な業務分担とされたが,Kの担当する製品の相談
やKに対する顧客からの苦情への対応依頼が原告に回ってくるなどし
た。
O部長は,原告からの数々の具体的な事実の指摘を伴う異動についての
切実な要望をことごとく無視し続けた挙げ句,既に精神的にも限界に達し
ていた原告に対し,「他に選択肢ないよ。この会社を辞めるか。」,「嫌
な中で,仕事だけやる。」などと二者択一を迫るとともに,退職を申し出
た原告を一切引き留めることなく即日退職手続を進めようとした。
(オ)被告の不法行為
以上の事実経過は,被告による原告に対する雇用契約上の使用者として
の不法行為又は債務不履行に該当するものであり,被告は,原告に対し,
これにより原告が被った損害を賠償すべき義務を負う。
イ 労働基準法37条違反の債務不履行又は不法行為
被告は,自己申告による労働時間が時間外労働の実態を反映していないこ
とを知りながら,あくまで労働時間の管理システムによって労働時間管理を
行い,原告ら従業員に対する時間外割増賃金の不払いを続けており,その悪
質性に照らせば,原告に対する債務不履行又は不法行為に該当する。
ウ 原告の損害
前記ア及びイの被告の不法行為又は債務不履行により原告が受けた精神
的損害は,少なくとも400万円を下回らない。
エ 小括
よって,原告は,被告に対し,上記損害金のうち348万2032円を賠
償を請求する権利を有する。
(2)被告の主張
ア 作為義務の不存在
(ア)原告の業務量を軽減すべき義務の不存在
原告は,被告が業務体制を改めて原告に過重な業務負担を強い続けてき
た実態を一日も早く解消すべき義務があったなどと主張するが,そもそも
原告がKと共同で行っていた業務の絶対量は一人でこなすことが十分
に可能な程度の業務量しかなく,原告がKを指導していたとも評価でき
ないから,原告の業務量が加重であったということはあり得ない。
また,Kが被告において4年以上業務を継続していたこと,原告入社
前はKが単独で業務に従事し,原告退職後は原告の後任者と共同で業務
を行っていることからすると,原告が主張する業務過多なる状態は,むし
ろ協調性のない原告が自らKとの協業を拒絶したがゆえに生じたもの
にほかならず,原告の主張は,業務過多の名を借りて自らが気にくわない
Kを排除したいだけのものであり法的保護に値しない。
よって,被告に作為義務が存しないことは明らかである。
(イ)職場環境を調整する義務の不存在
Kによるパワハラの訴えは,原告を陥れる目的で申告したものではな
く,原告がKに対して同僚に対する業務上の助言を超えた,名誉権を侵
害し得る暴言があったことによるものであり,Kのパワハラの訴えは,
正当な権利行使である。原告及びKがパワハラの有無で紛争となった相
手と共同で業務を行うことについて心情的に認め難い気持ちがあっても,
このような関係の悪化は単なる個人的な好き嫌いの感情を超えない,法的
保護に値しないものであって,両者いずれかによるハラスメント行為があ
ったと認定できない段階で,被告に配置転換をすべき義務があったとは評
価できない。
被告は,使用者として原告に対して人事権を有しており,原告及び、K
に対する業務割当てにつき広範な裁量権を有する。被告は,いわゆる外資
系企業であるから,終身雇用を前提としてジョブローテーション制度を
採用している日系企業と異なり,人事異動を行うことが極めて困難で、ある
ことから,Kの能力不足が客観的に示され,単なる原告及びKによる
従業員同士の不和を超えるものとの認識があって初めて回避義務として
両者のいずれかを異動させるべき義務が生ずるところ,これに至らない程
度であれば,業務の適正な運営の必要から,両者に対する個別的説得,第
三者を仲介者としての仲裁,メンターを付けての業務執行等が通常合理的
な対策であるといえる。
被告が果たすべき安全配慮義務は,職場において,通常,いじめ等によ
り原告が生命・身体に対する具体的な危険が生じない限度で足りるもので
あり,それ以上に原告が希望する就労環境を提供しなければならない法的
義務は存しない。
イ 作為義務違反が存しないこと
仮に,被告において原告の過重な業務につきKとの業務分担について
適切に調整する義務等が存したとしても,被告においては,可能な限り原告
の意見を反映しようと様々な対策を行っているから,被告が作為義務を果た
したことは明らかである。
ウ 損害及び因果関係が存しないこと
本件においては,原告に,過重業務により具体的な生命・身体に対する危
険及び損害があったことが明らかになっておらず,填補すべき損害が存しな
い。原告は,退職を余儀なくされたことにより被った損害を主張しているが,
被告は,原告を解雇していないばかりか,退職勧告等もしていないから,原
告の上記主張は失当である。仮に退職に至ったことで何らかの損害が発生し
たとしても,被告は,原告が退職日以降も被告において就業することを何ら
妨げていないから,原告の退職の意思表示という原告白身の行為によって損
害が発生したものであり,被告の不作為と相当因果関係があるとはいえない。
エ 過失相殺
原告の一連の行為は,単に自身の気に入らないKの行動を針小棒大に評
価し,何ら自身に危害が発生しておらず,かつ,その具体的なおそれがない
にもかかわらず,断固としてKとチームとして行動することを拒否し,被
告の緩和対策についても一顧だにしないだけでなく,自らの自由な意思で退
職を決意したのに,被告に対して何ら対策を採らなかったと避難するなど,
通常の従業員であれば取り得ない行為をとった原告が,退職により何らかの
損害が発生したとしても寄与度は原告にあり,被告がかかる責任の全てを
負うべき理由はない。
オ 小括
よって,本件において,被告に不法行為責任又は債務不履行責任が生ずる
ことはないから,これらに基づき被告が原告に対して損害賠償義務を負うこ
とはない。
第3 争点に対する判断
1 認定事実
前記前提事実及び当事者聞に争いのない事実に加え,後掲各証拠(後記認定に
反する部分を除く。)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(1)原告が被告に入社した経緯
原告は,被告の前身会社に平成18年1月から正社員として勤務し,インス
トールサポートを単独で担当していたが,体調を崩したため,平成19年5月
に退職した(甲9・1頁)。
原告は,平成21年1月13日に被告による経験者募集の求人に応募したが,
O部長から,被告の経営状況がよくないため採用を待ってもらうかもしれない
旨の連絡を受け,その後,平成22年5月になって被告の入社面接を受けたが,
被告から採否の連絡がなかったため,同年7月8日にO部長に対してメールで
辞退の意向を伝えたところ,O部長から,誤解である旨の連絡が直ちにあり,
最終的に,同年10月1日,原告は,雇用期間を同日から1年間と定めた雇用
契約を締結して被告に入社した。(甲9・1,2頁,甲61から67まで,原
告本人・3,4頁)
(2)原告の入社に伴う技術部内の体制の変更
原告が被告に入社する前は被告のインストールサポートはKが専任とし
て従事していたが,インストールサポートの業務全般のうち少なくとも5割程
度は技術部において行うほか,Kのパックアップ業務など一定の業務は,被
告の情報システム部(以下単に「情報システム部」という。)が暫定的に担当
することになっていたため,原告入社後の平成22年10月9日及び同月28
日,情報システム部部長のM■■(以下「M部長」という。)は,O部長
に対し,メールで,原告の入社に伴い同年11月1日以降は上記業務を完全に
技術部に移管させてもらいたい旨を依頼した(甲52の1及び2,甲74,7
5,原告本人・74,75頁,弁論の全趣旨)
(3)原告入社後間もなくの状況
ア 原告は,被告への入社後間もなくして原告入社前のKによるインスト
ールサポートの状況について技術部員等から実態を聴取したところ,Kに
仕事を依頼しても何も解決せず完全に信頼関係が切れている,いくら言って
もやらず,間違ったサポートや放置をするから信用できない,Kに頼むな
ら自分でやる方がよい全くやらずにただIT部門に投げるだけ,すぐにや
ってくれず顧客から苦情が出る,顧客からK以外の人に対応してもらいた
いと要求されるので技術部では自分達でライセンスサポートをやるように
なった,O部長に別な人を依頼したが何もしなかったなどの話があり,技術
部のテクニカルアドミニストレーター(技術部におけるアシスタント業務全
般を担当する部員)からは,FAQ(Frequently Asked Q
uestions(よくあるご質問))を大量に作り,勝手な独自のルール
で意味のない作業ばかり要求してくる,技術部のサポートルールを守らず,
何度言っても同じことの繰り返しであるなどの話が寄せられた。原告は,こ
れらの話を聞き,また,実際にKと一緒に仕事をしてみて,Kがインス
トールサポートにおいて,自分独自の考えを押し通し,原告や技術部内又は
他の部署からの依頼に対して自分の佐事ではないと断ることが多く,他方で
FAQを大量に作成し独自のルールで必要性の低い作業を要求するなどし
ており,Kと技術部のエンジニア等との間で信頼関係が崩れていると認識
した。そこで,原告は,O部長にインストールサポートの体制(以下「サポ
ート体制Jという。)等について打合せをしたい旨の相談をし,平成22年
10月17日には,O部長に対し,今後のサポート体制についての案として,
「Kさんを月曜日のGL会議への強制参加(皆さんの意見や要望を聞くよ
うに促し,独自路線に走らないようにするのが目的)」,「インストールサ
ポート等のFAQ/インストールガイド作成等も技術部の承認・打合せ必
須」などを挙げた上,「2名体制となりましたが,Kさんと社内での信用
関係が予想していた以上に厳しく,Kさんはほぼ暴走に近い状態で,皆さ
んの意見は全く聞かない状況です。」,「今後2名体制で行っていけるかど
うかもそもそも不安な感じですが,まずは上記の方法等で,Kさんが少し
ずつでも皆さんの信用をとりもどせる体制づくりも一緒に考えてみてはい
かがでしょうか。」などと記載したメールを送信した(甲20の2,甲46,
47,原告本人・75頁から77頁まで)。
イ FAQに対しては,顧客がウェフサイトから意見・要望等をアンケートメ
ールとして投稿することができるところ,平成21年11月12日以降,
Kの作成したFAQに対して,「FAQを増やすのではなく,どうやったら
FAQを見なくてもスムーズにインストールが完了するのかという方向で
インストールマニュアルを見直す必要があるのではないでしょうか?J,「F
AQを増やせばいいというものではありません。考え方を変えて根本的な解
決をしていただきたい。」,「WEBページの構成が見づらいです。」,「自
己満足ページではなく,相手に分かつてもらえるページの構成にしてくださ
い。」,「要望への対応に関しては,改善の余地があると思います(要望に
ついてはこれまでに対応してもらったことが無い)。」(以上甲47),「ラ
イセンスマネージャーが起動されていないときの起動方法が書かれていな
いので,このヘルフじゃ不十分。読むだけ時間の無駄でした。fluent
のライセンスマネージャの種類(パージョン)が多いため,訳が判らない。」
(甲55の1)などの意見が寄せられていた。
原告は,入社後間もなくの平成22年10月15日,技術部のYから,
インストールサポート関連のFAQだけがまだ整理されていないとの相談
を持ちかけられ,原告が同FAQの整理を行うことになった(甲46,48,
49,56,57)。
ウ 平成22年10月21日,原告は,O部長と住事の分担について協議し,
また,同月28日にはサポート体制についての今後の方針案等をメールでO
部長に伝えるなどしていたが,状況に変わりがないため,同年11月14日,
同月1日から同月11日までの10日間のサポート状況についてまとめた
資料を添付して,O部長に対し,関係者を含めて相談の機会を持ちたい旨を
メールで伝えた。なお,上記の資料には,上記10日間におけるサポート件
数が原告18件であるのに対してKが5件であること,技術部からの依頼
の対応件数が原告11件であるのに対してKがO件であること,原告や技
術部からの質問や依頼に対するKの具体的な対応状況等が記載されてい
た。(甲17の1及び2,甲20の3)
(4)チームリーダーへの指名
平成22年11月17日,O部長,原告及びKの3名で打合せが行われ,
その場で,O部長は,Kがサポートの依頼を受けないことへの対応として,
原告をチームリーダーに指名し,原告に対し,チームリーダーとしてKへの
仕事の割り振りや指導を行うよう指示した。原告は,有期雇用契約の従業員の
立場である自分がチームリーダーとして正社員のKに対して指示・指導をす
るのは自分の業務範囲を超えていると思ったが,O部長からの指示であったた
め,以後,原告が,顧客等からサポートの依頼があった場合にその担当者の割
り振りをし,Kの担当分として割り振った案件をKに依頼した。なお,上
記打合せの際に,Kが原告に対して「命令するな。」と言ったため,原告は,
Kに仕事の依頼をする際には丁寧に依頼するように心掛けていた。(甲8・
4枚目,甲9・5頁,甲53の4,証人O・11,12頁,原告本人・21,
22,77,78頁)
しかし,原告が口頭でKに業務を依頼しでも,Kは,これは自分の住事
でないとか,できないなどと様々に理由をつけて拒否したため,原告は,紙に
印刷して本人に説明した上で直接手渡すという方法を試みたが,Kがその紙
を捨てたりシュレッダーにかけたりしたため,最終的にはメールで業務を依頼
するようになった(甲27の1,原告本人・23頁から26頁まで)。
(5)平成23年1月から同年8月頃までの状況
ア 平成23年1月5日,原告は,O部長に対して,メールで,平成22年1
1月及び同年12月のサポート件数の結果をまとめたものを報告するとと
もに,同結果について,アンシス(ANSYS)製品については原告がほぼ
7割以上でKのサポート件数が減少していること,口頭ベースでの問い合
わせ等はほぼ原告が対応している傾向があることなど,分担が不均衡になっ
ている旨を伝えた。このメールを踏まえて,O部長,原告及びKで打合せ
が行われたところ,Kが「原告がサポート案件を振ればやります。」と述
べたため,原告がサポート案件をKに振るようにして様子をみることにな
った(甲8・8枚目,甲19の2,甲20の5)。
イ 平成23年3月29日,原告がKに対し,担当業務を行っていない旨の
指摘をしたところKが「自分の仕事ではない。」と言って原告と口論に
なった。O部長は自席にいてこの様子を聞いていたが,何もせず,また,周
囲もただ傍観していた。同日の夜,原告は,O部長に対し,「Kさんに話
をして頂けると期待していたのにとても残念です。これまでずっと技術の
方々,Mさんを含め,Kさんをマネジメントできなかったように,これ
以上は自分もできません。(中略)彼が担当業務を満足に行ってくれないの
は,すでにAJKの皆さんが周知の事実です。それでもKさんが必要とい
うことであれば,自分がここで頑張る意味もありませんので,どうかAJK
全体として真剣に考えてください。」と記載したメールを送信し,また,平
成23年4月2日には,「半年間ですが,Kさんと仕事をすることは難し
いと何度か申しあげたかと思います。インストールサポート関連全般の仕事
は協力してやって頂けないことは十分に理解しました。今後は無駄ですので
こちらから依頼もしません。マネジメントという意味では,自分もKさん
の指導はできません。」などと記載したメールを送信した。(甲8・12枚
目,甲9・5,6頁,甲20の7)
ウ 平成23年4月2日,顧客から被告のライセンス担当者宛てに「教えて頂
いた方法を試してみましたが,ライセンスマネージャーはやはり起動しませ
んでした。」とのメールが送信されたため,原告は,Kに対し,顧客対応
の不適切な点を指摘するメールを送信した(甲20の6)。
エ 平成23年4月11日,同日にサポートを約束していた顧客から「本日,
インストールについてご連絡頂けるとのことでしたが,その後,どうなりま
したでしょうか?」との問い合わせのメールがあったため,原告は,同メー
ルをO部長に転送して状況を報告した(甲18の4)。
平成23年4月22日,原告は,顧客から「サポートとしてKさんの対
応がちょっとひどく今後は気をつけていただきたい。」との苦情を受けたた
め,O部長に状況を報告した(甲18の2)。
平成23年5月9日,Kの顧客に対するインストールサポートの対応が
不適切であったため,技術部員のZ■■(以下「Z」という。)がサポ
ートを引き継いだ。Zは原告及びO部長等に対し,経緯を説明した上で
「今回のようないい加減な対応は非常に困ります。」などとメールで伝えた
ととろ,原告は,Z及びO部長に対し,O部長と担当グループを含めて今
後の対応方法等について相談したい旨をメールで連絡した。(甲18の3)
オ 原告は,O部長からKに足りないスキル等の問題についてリストにして
メールするよう指示されたことを受けて,平成23年5月16日,Kの技
術及びサポートスキルの問題としてITエンジニアとしての最低限の知識
不足,根本的な問題を捉えようとしないための問題解決能力不足,優先順
位・緊急性の有無等による迅速かつ正確な対応能力不足などを具体的に列挙
した上で,「この部署では通常の製品サポートと異なり,緊急性も高く,迅
速,正確な対応が必要であり,簡単なオペレータ的対応でよいという仕事は
少ししかありません。」,「状況が変わっていない点を考慮すると,残念な
がらこの部署の仕事は厳しい,また向いていないと判断せざるを得ません。」
などと記載してO部長宛てにメールを送信した(甲8・16枚目,甲70)。
カ 平成23年5月20日,O部長,原告及びKとで打合せを行い,O部長
は,原告に指示して作成させた「ライセンスサポートの心得」と題する資料
を用いて,Kに対し,サポート品質向上のための指導を行った。上記資料
には,ライセンスサポートの心得として,「すぐに対応する。」,「一発解
決,短時間解決を心掛ける。」及び「問題解決の為に社内エンジニア,営業
に確認する。」の3項目を掲げた上で,各項目について,顧客満足度を上げ
るためのサポートの具体的な心得が記載されていた。(甲8・16枚目,甲
71の2)
キ 平成23年6月27日,原告は,O部長に対し,メールに「結局,昨年の
10月以降なにも状況は変わっていないと思います。」,「ルールを守れな
い。直接言っても,聞いていない,わからないで逃げる。サポートもできな
い→増やせば苦情が出る。コミュニケーションもとれない。」,「なんど話
合いをしても改善がなく,いつまでも甘やかしても仕事もせず,お客様の苦
情がくるのでは本当に迷惑です。」などと記載しKの部署異動等を真剣
に考えてほしい旨要求した(甲20の8)。
ク 平成23年7月4日,原告は,O部長に対し,メールで,同年1月から同
年6月までのインストールサポート状況について集計した結果を連絡する
とともに,同年4月以降,インストールサポートにおいてKに関する状況
が変わっておらず,ほとんど仕事を任せられない状況であるため,Kをラ
イセンス発行等簡単な業務の部署へ異動させることを検討してほしい旨を
改めて訴えた(甲19の4)。
ケ 平成23年7月12日,原告は,O部長に対し,メールで,「これ以上,
本人との話合いは全く意味がなく時間の無駄です。」,「8月以降は,お客
様サポートは自分に任せて下さい。」「事実上この業務は既に自分がほと
んど行っています」などとしてサポート体制の変更等を求めたところ,O部
長から何ら応答がなかったため,同年8月5日頃にも,同月以降のサポート
体制として,原告を顧客に関わるサポート全般としKをSecond
Line Supportのみとする体制を要望するメールをO部長宛て
に送信した(甲8・20枚目,甲20の9)。
(6)Kによるパワハラの訴え
ア 平成23年8月18日,原告が営業部員から直接サポートの依頼を受けて
顧客対応中であった案件について,顧客から電話で要求されたという事情等
が存しないにもかかわらず,Kが原告に無断で上記顧客の対応を引き継い
で行うという出来事があったため,原告は,Kに対し,O部長及び技術部
の全員をCCの宛先に加えたメールで,「人がサポート中の案件に勝手に手
を出さないでください。」などと注意した。また,同日,原告は,O部長に
対し,「人がサポートしているのを途中から奪い取ったり,都合の悪いお客
様宛てのメールを削除したりと最近の行動は普通ではなく目に余ります。」
などと記載してKをライセンスサポートから外すようメールで要求した
(甲25の5及び8)。
イ 平成23年8月19日以降,Kは,電話やメールに対応せず,内線電話
にも出なくなった(甲8・22.枚目,甲74)。
ウ 原告は,Kがいつもと異なる様子であると感じたため,同月28日,出
張中のO部長に対し,メールで,「8/19以降,Siebelを除き,電
話/サポートメールは一切行わず,電話も取りません。しかし,勤務時間中
になんらかのメール送信・チェックを行っておりこれまでとは異なりなん
らかの恐怖を感じています。」,「これ以上は彼への対応は不可能です。自
分としてできることは,お客様に迷惑をかけないよう,休暇は取得せず,サ
ポートに全力を尽くすつもりですが,すぐに解決するとは思えません。」な
どと連絡したところO部長は,原告に対し,「今の状態はよくないことが
分かっています。これ以上悪化すると,技術部にだけではなく,会社全体に
トラブルが起こるリスクが有ります。私が木曜日に帰国し,今週金曜日出社
の時に直ぐ対応します。」と記載したメールを返信した(甲25の9)。
エ 原告は,Kの様子がいつもと異なることから,KのPCにアクセスし
てみたところ,Kが,原告の平成23年8月18日付けのKへのメール
(前記ア)のほか,原告がKに対し,仕事剥奪,正論を装った個人攻撃及
び「おまえなんか会社に来なくていい」等の発言を行っており,これらが
Kに対するハラスメントに当たる旨主張して,O部長に対し,対処を求める
文書を作成していることがわかった(甲9・6,7頁,甲26の1及び2)。
オ 平成23年9月2日,原告は,出張から戻ったO部長から呼び出され,
Kが原告からパワハラを受けたとして被告のコンブライアンス機関に訴え
たこと,パワハラが認められれば懲戒解雇の可能性もあることを告げられた。
原告は,Kのこれまでの問題行動等を改めて指摘し,全てについて調査を
するよう求めた。そして,原告は,同日の夜,O部長に対し,メールで,「疑
いが晴れるまで自粛するのがよいかと思いますので,出張前に以下の承認を
お願いします。」として,Kのサポート未対応分の確認及びライセンス関
連のサポート・電話対応を全てKに依頼することを求めるとともに,「8
/19~8/26以降こちらもいつも違う殺気だったものを感じます。非
常に怖い思いをしているため,もう一つ席を移動させてください。」と依頼
した。これに対し,O部長から,暫定的な仕事の分担を同月5日に話す旨の
返信があったが,原告は,「これまでに50%:50%→苦情→70%:3
0%やってきても,結局は同じ繰り返しになっており全く解決していないの
ではないですか?製品を分けたとしても意味がありません。現在,ライセン
ス関連自体のサポート件数も多くないですし,技術部・営業さんは自分に直
接依頼しにくるので一度まかせるべきです。」などと記載したメールをO部
長に送信した。(甲8・24枚目,甲9・7頁,甲25の10,原告本人・
28頁)
平成23年9月3日,原告は,座席を一つ隣に移動させた(甲8・23枚
目,乙8の1及び2)。
カ 平成23年9月7日,原告は,被告人事部部長のR■■(以下「R部長」
という。)から要請を受け,同日,平部長及びO部長との面談を受けた。ま
た,同月2日から同月7日にかけて,人事部による技術部の聞き取り調査が
行われ,これまでのKの勤務態度やトラブルについて聴取された。なお,
原告のパソコンの調査も行われたが,被告からIT規範に違反するなどの指
摘がされることはなかった。(甲9・7,8頁)
キ 平成23年9月16日,原告は,O部長及びR部長に呼び出され,パワハ
ラの事実はなかったことを告げられた上で,今後3か月間Kの指導をする
よう指示を受けたため,「自分はとても精神的に無理なので,権限のある人
で指導してください。」などと回答した。原告は,複数の技術部員らに,「結
局仲良くやってくれと。3ヶ月様子をみてくれと。無理です」と記載したメ
ールを送信するなどして相談し,同月17日にはO部長に対し,何度も考え
てみたがKを3か月間指導するのは精神的に不可能であること,精神的に
も非常に苦痛でありこの状態のまま現在の仕事自体を続けることができず,
とても指導できる状態ではないことなどをメールで訴えたところ,同月20
日,O部長から,Kと一緒に仕事ができないことは理解したと言われたが,
原告としては,O部長が本当に理解しているか疑問に感じた。(甲8・24
枚目,甲9・8頁,甲25の12,甲72,73,原告本人・64,65,
79,80頁)
(7)インストールサポートで用いるメール機能の変更
技術部におけるサポート業務は,個人ごとのメールアドレスで対応していた
が,原告及びKだけは,顧客サポートの専用ソフトである「サイボウズメー
ルワイズ」を使用してインストールサポートを行っていた。サイボウズメール
ワイズでは,顧客からのメールは原告やKの個人のメールアドレスには送信
されず,ログインしなければメールを見ることができない仕組みとなっていた。
原告は,サイボウズメールワイズでは隔離・閉鎖された環境でインストールサ
ポートが行われることになり,その実態を技術部員が直接確認することができ
ないことから,顧客からのメールが個人のメールアドレスにも配信される仕組
みにするよう求めていたところ,平成23年9月29日頃に原告及びKのメ
ールアドレスに配信されるようになり,また,平成24年7月1日からは,技
術部全員に配信される体制に変更された。(甲9・6頁,甲31の1から31
の3まで,弁論の全趣旨)
(8)平成23年10月からの体制
平成23年9月28日,O部長は,技術部の全員に対し,同年10月1日か
ら同年末までのインストールサポートの割り振り等について,①被告の技術部
のグループリーダーであるT(以下,単に「T」という。)が調整・相談
役を担当し,負荷の調整,トラブルの未然防止,技術指導と相談など,実質的
にチームリーダーの役割を果たし,最終責任はO部長が持つこと,②原告及び
Kは,製品別で毎月ローテーションしながらインストールサポートを分担し,
一方の不在時(出張,休暇等)には他方がその期間に全部のサポートを担当す
ることなどをメールで伝えた(甲25の13)。
平成23年10月から同年12月までの間,原告とKとの分担は上記②の
とおり製品別で行われたが上記①については,Tが調整・相談役としての
役割を効果的に果たすことはなかった。(証人O・39頁,原告本人・34,
35頁)。
平成23年11月24日,出張中の原告の携帯電話にO部長から,原告と
Kの席を移動させ隣接させることとした旨の連絡があった。原告は,隣席の
Kからパワハラで訴えられた恐怖から,再び隣席で住事をすることは精神的に
も耐えられないと思い,技術部員に相談するなどしていた。(甲8・28枚目,
甲9・9頁,甲25の17)
(9)平成24年1月以降の執務状況等
ア 平成24年1月初めにT及び、ZとO部長との聞でシステムサポートの
問題について話し合いが持たれ,技術部全体でパックアップする案も出され
たが,O部長が了解しなかった。同月10日には,O部長,T及び原告と
でサポート体制についての話し合いが持たれ,T及び原告は,Kが合併
前の旧アンソフト・ジャパン株式会社(以下「アンソフト」という。)の製
品のサポートを,原告がその他アンシス製品のサポートをそれぞれ担当し,
原告のパックアップは技術部が行う体制を要求したが,O部長は,サポート
の分担については了解したものの,原告のパックアッフについてはKがす
ることとし,うまくいかなければ再度検討することとした。(甲8・32枚
目)
イ 平成24年1月から同年3月上旬頃までの期間は,暫定的措置として,原
告はサポート業務から外れて新製品のマニュアル作成業務を担当し,Kが
ほぼ全てのサポート業務を担当していたが,Kの担当したサポート業務に
関する苦情が原告に回ってくることもあった(甲8・32,34,36枚目,
甲74,原告本人・35頁から37頁まで)。
ウ 平成24年2月24日,原告は,O部長に相談した上で,再びKの席と
離れた場所に座席を移動させた(甲8・33枚目,甲29の1及び2,乙8
の3)
エ 平成24年3月6日,O部長は,被告の全従業員宛てに,同月12日から
実施するインストールサポートの新しい分担として,原告が「FBU・MB
U製品Jを担当し,原告不在の期間における緊急の電話対応・サポートは
Kが行い,Kが「EBU(Ansoft)」を担当しTがこれをバック
アップすることとする旨をメールで連絡した。原告の担当とされた製品は,
平成23年10月1日からのサポート体制において原告及びKの二人で
分担していた製品を全て含むものであり,サポートの量で比較すれば,原告
の担当とKの担当は7:3程度の割合で原告の負担が多い分担とされてい
た。(甲25の13,甲30,甲71の3,甲74,原告本人・37頁から
39頁まで)
オ 平成24年3月15日,原告は,Tに対し,Kに対する苦情への対応
依頼が同月14日,同月15日と続いている上,他の苦情案件も回ってくる
可能性があることを伝えてKへの指導及びO部長への報告をメールで依
頼した(甲28の3)。
平成24年3月16日,被告の営業部員からTに対し,Kに対応を依
頼していた顧客からクレームの電話があり「全く情報をもらえず話になら
ない。今日中に回答をほしい。」と厳しい口調で言われたこと,原告に相談
してすぐに顧客に連絡して対応し顧客の納得を得たこと,原告がいなければ
顧客を奪われていた可能性もあること,このようなことが続くと顧客の信頼
を失いかねないので改善をお願いしたいことなどについてメールで連絡が
あり,これに対し,Tは「商談に影響が生じるというのは非常に大きな問
題であると認識しています。今後はこのようなことが起きないよう対策を考
えます。」などと返信した(甲28の4)。
カ 平成24年6月25日,原告は,O部長及びTに対し,メールで,新体
制によるKの原告に対するパックアップ体制が機能していないことを指
摘した上で,Kに対するパックアップ体制と同様に,原告についても技術
部内でのパックアップ体制をとることの検討を依頼した。同年7月9日には,
ZがO部長に対し,原告の不在時や仕事量の多いときなどに原告のパック
アップを自分が引き受けてもよい旨の申出をしたが,サポート体制は特に変
更されなかったため,同年8月13日,原告は,同年10月に夏季休暇を取
得するに先立ち,O部長に対し,Kによるパツ,クアップ体制がほぼ機能し
ていない状況であることを指摘した上で今後のサポート体制の検討を再度
依頼した。(甲20の10及び11,甲34)。
キ 原告の複数回の依頼にもかかわらずサポート体制が特に改められること
はなかったため,原告は,平成24年9月7日(金)に不在となるのに先立
ち,その前日に,被告の全従業員に宛てて,同月7日が不在となること,シ
ステム関連の電話サポートの連絡があった場合には月曜日に折り返し対応
する旨を顧客に連絡すること緊急の場合はO部長に相談することを依頼す
るメールを送信した。しかし,同月7日の朝に顧客から問い合わせのメール
が送信されていたにもかかわらず,同メールが同日の夕方まで放置された状
態になり,これに気づいた技術部員が同日中に電話及びメールで対応すると
いう状況であった。原告は,同月7日の状況について報告を受けて,O部長
及び技術部の全部長に対し3月の新体制下で原告が担当するFBU・MB
U製品サポートに関してパックアップ体制が機能しておらず実質的に1名
体制となっていること,今回のように緊急度の高いサポート依頼が放置され
るのは非常に問題であること,基本的に休まないつもりでいるが原告の不在
時に緊急性の高いものは技術部からフォローする体制だけでもお願いした
いことをメールで訴えた。(甲20の12から20の14まで)
ク 平成24年10月5日,原告は,被告代表者宛てに,「今後業務を続ける
に当たりやむを得ず事実を把握して頂きたく要望書として提出致します。」
などと記載し,「労働条件の向上と安全な職場環境を求める要望書」と題す
る原告作成に係る被告代表者宛ての書面を添付したメールを送信した。これ
に対し,被告代表者から原告に対し,要望の背景と要望内容について会社と
して十分注意して検討した上でどのように対処すべきか等を回答したい旨
記載されたメールを返信されたが,その後,被告代表者から原告に対し回答
はなかった。(甲8・50枚目,甲9・10頁,甲37の1及び2)
ケ 平成24年10月9日から同月12日までの間,原告が休暇を取ったため,
その間,Kが電話サポート等9件を対応しKはその旨をO部長や原告
に報告したが,原告は,O部長及びTに対し,原告の休暇中3件が未対応
になっていたこと,会社として24時間以内に回答し不在期間はパックアッ
プするとの方針になっているにもかかわらず1週間で3件ものサポートが
見過ごされるのは非常に問題であることを指摘した上でサポート体制の改
善を求めた。そして,原告は,平成24年11月8日,人事部部長のH(以
下「H部長」という。)宛てに,「数年前から何も変わっていない実情だ
けでもご理解いただきたく本件について転送させていただきます。」として,
上記の原告のO部長及びT宛てのメールを転送した。(甲32の3及び4,
甲39)
コ 平成24年12月10日,原告は,Tに対し,メールで,アンソフト製
品の担当であるKやそのパックアップを担当するTが不在のことが多
く,アンソフト製品のシステム・ライセンス関連の相談が原告にされるが,
アンシス製品のサポートに加えてアンソフト製品関連の相談に乗る余裕が
ないので,アンソフト製品担当のグループ内で対応してもらいたい旨を依頼
した。これを受けて,Tは,同グループの担当者等に対し,原告はアンシ
ス製品の担当であり,アンソフト製品の担当はKであるから,原告にアン
ソフト製品のインストール等に関する問題を質問しないよう依頼するメー
ルを送信した。(甲28の2)
(10)退職に至る経緯
ア 平成24年10月18日,原告は,H部長と面談し,Kと一緒に佐事
をするのは不可能である旨を説明したが,H部長から,部署異動等につい
ては年内は待ってほしいと言われ,また,平成24年11月8日には,O部
長から,異動も検討するが12月まで待ってほしい旨を告げられた。(甲8・
49,50,52枚目,甲38,原告本人・63頁)
イ 平成24年12月26日,原告は,部署異動等について再度確認するため,
O部長と面談した。面談の当初,O部長は,原告に,事務系も含めて部署異
動は無理である旨を告げた。原告は,O部長に対し,状況がずっと何も変わ
っていないこと,Kと一緒に働くのはあり得ないこと,個別具体的な業務
に関し原告一人では時間がなく対応が無理であること,誰かバックアップを
してほしいと言っていても対応されないこと,技術的にできないと事前に説
明しでも営業部員等が話を進めてしまい,結局,原告に仕事やクレーム処理
が振られることになることなど,自身が置かれている窮状を訴えたが,O部
長は,概要「Kが嫌なのはわかるが仕事上で影響が出たら他に選択肢は
ない。この会社を辞めるかこの状況の中でやるべき仕事をやるか。Kの
件については,進展はないもののいろいろやった。それがもう自分の限界を
超えているから,今後の判断は原告に任せる。自分としては,原告にやって
もらいたいが,他に更に良い環境はもう限界である。」と述べた。このよう
なO部長の対応に対し,原告は,「自分から見たら何も変わっておらず,誰
もフォローしてくれないのに責任ばかり持たされるのは,無責任である。」
旨述べ,上記面談後の同日中にO部長に対しメールで,平成24年12月2
8日を最終出社日として退職する旨の申出をした(甲41)。
ウ 平成24年12月27日の朝,O部長は,原告を呼び,原告の退職の申出
を了解した旨告げて,人事部に話をするため,前日の原告のメールを印刷し
た紙に署名するよう原告に求めた。その後,原告は,H部長と退職手続の
ための面談をし,退職理由について確認の上,同日付けで,退職理由を「一
身上の都合の為」、と記載した退職願を被告に提出した。(甲3,甲9・11
頁,甲42)
エ 平成24年12月28日被告の技術部員に対し,原告が今年で最後にな
るためインストールサポートは各グループで各担当者が行うことになった
こと,手に負えない問題が生じた場合に備えてシステム構築専門業者と契約
する予定であることがメールで伝えられた(甲45)。
原告は,退職に際し,O部長宛てのメールで,お礼を述べるとともに「2
010年に受けた件は,これまで生きてきた中でも最も大きな精神的ダメー
ジであり,自殺も考えたほど今でも精神的恐怖を感じています。」,「この
ような状態が1年以上続いた上で,解決策がないのであればこの決断しかな
いことは十分にご理解頂いているものと思っておりましたが,上司,信じて
おりました思師としてご理解頂けなかったことは非常に残念です。」などと
伝えた(甲44)。
(11)あっせん申請
原告は,平成25年1月10日に東京労働局に相談した上で,同月11日,
あっせん申請書にあっせんを求める理由として「職場の改善要求を1年以上訴
えたにもかかわらず,全く改善されることもなく,非常につらく,本来の業務
以上の責任,過負荷を強いられた上で不本意な退職をさせられた。」などと記
載して,あっせんを申請したが,同年3月22日,同申請を取り下げた(乙2,
3)。
2 甲8,46号証等の信用性について
被告は,甲8号証が本件提訴後にその存在が被告に明らかにされたこと等を根
拠に,その作成経過には強い疑いが持たれるなどと主張する。
甲8号証は,原告の日々の出勤状況や勤務状況が記載されたノートであるとこ
ろ,その作成経過について原告は,日にちと曜日は1か月ごとに月初めにまと
めて記載し,日々の通勤の際に持ち歩き,出勤した際に始業時刻を記載し,その
日の出来事や退社時刻は携帯電話や手帳にメモした上で帰宅後に甲8号証のノー
トに書き込む旨述べる(原告本人・7,15,16頁)。また,甲46号証及び
甲53号証の4は,原告が参加した打合せの内容等について記載された,甲8号
証とは別のノートであるところ,その作成経過について,原告は,普段は職場の
原告専用のキャビネットに入れて保管し顧客との打合せや社内での打合せの際
にノートを打合せの場に持ち込み,その場で参加者の発言等を記載していた旨述
べる(原告本人・7,8,73頁)。そして,これらのノートにメモを残した理
由について,原告は,日々の生活の中でも「言った」「言わない」の食い違いが
生ずるため,従前から日々メモをとることを習慣としていた旨を述べる(原告本
人・7,73頁)。
原告が述べるこれらのノートの作成経過等に不自然なところはなく,また,こ
れらのノートに記載されている内容はいずれも具体的で発言者等の関係者も特定
されており(甲8の46,甲53の4),本件提訴に当たって事後的に作成した
ものとは考え難いこと及び弁論の全趣旨によれば,甲8号証のノートについては
日付以外の部分は基本的に当日又は数日後以内に記載され,また,甲46号証及
び甲53号証の4のノートについては打合せの場で記載されたものと認めるのが
相当であり,原告の上記供述及び前記認定事実に掲記した証拠との整合性に照ら
せば,その記載内容についても信用性があると認めるのが相当である。
よって,甲8号証等のノートの記載は信用性がない旨の被告の主張は,理由が
ない。
3 被告の不法行為又は債務不履行について
(1)被告の注意義務
使用者は,その雇用する労働者に対して業務の指示・管理をする権限を有す
るから,当該労働者に従事させる業務を定めてこれを管理するに際し,業務の
遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して労働者の心身の健康を損なう
ことがないよう注意する義務を負うと解するのが相当であり,使用者に代わり
労働者に対し業務上の指揮監督を行う権限を有する者は,使用者の上記注意義
務の内容に従って,その権限を行使すべきことになる(平成12年3月24日
最高裁第二小法廷判決・民集54巻3号355頁参照。労働契約法5条)。
そうすると,本件において使用者である被告は,その雇用する労働者である
原告に対し,業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して心身の健
康を損なうことがないよう注意する義務を負い,原告に対して業務上の指揮監
督を行う権限を有するO部長は,被告の上記注意義務の内容に従って原告に対
する指揮監督権限を行使する義務を負う。
(2)本件における被告の具体的な注意義務について
原告は,玉部長には,原告に過重な業務負担が強いられ続けている状況や原
告からの配置転換に関する切実な要望について適切な対応をすべき義務があっ
た旨主張するのに対し,被告は,原告が主張する業務過多なる状態は協調性の
ない原告がKとの協業を拒絶したために生じたものであり,また,Kのパ
ワハラの訴えは正当な権利行使であって原告及びKの関係の悪化は単なる個
人的な好き嫌いの感情を超えないものであるからいずれも法的保護に値しない
として,原告主張に係る義務はそもそも存しない旨主張するので,まず,この
点について検討する。
ア 原告の業務負担の状況について
(ア)Kに関する業務遂行上の問題について
被告は,原告入社以前からKは特段大きな問題もなくインストールサ
ポートを一人でこなしており,原告を採用したのもKの不在時のパック
アップ要員として採用したものである旨主張し,O部長らは概ねこれに沿
う旨述べる(乙9・2,3頁,乙10,11,証人O・7,10,14,
36,37頁)。
しかし,そもそも被告は,Kとコミュニケーションを十分にとること
ができることが採用条件であった旨主張し,O部長も原告の採用に当たっ
てはKとチームを組めることが重要であり,大きな選考要素となってい
た旨述べる(乙9・2,3頁,証人O・10,34頁)が,O部長が述べ
るように,Kが,仕事は十分にこなすものの社内でのコミュニケーショ
ンに関して多少のスキルアッフを要する程度であった(証人O・10,3
6,37頁)というのであれば,Kとチームを組めることが大きな選考
要素にまでされることは考えにくい。そして,前記認定事実(2)によれば,
原告の入社前は技術部及び情報システム部のサポート文はバックアップが
あって初めてインストールサポートが業務として回る状況であったと考え
られ,また,前記認定事実(10)エのとおり,被告が,原告の退職に伴い直
ちに,サポート体制を「各グループで各担当者が行い,手に負えない場合
に備えてシステム構築専門業者と契約する」とする新しい体制に変更して
いることに照らしてもKが一人で特段の問題なくインストールサポー
トをこなせる状態であったとは考え難い。
そして,原告が入社後直ちに技術部員等から聴取したKの業務遂行状
況が前記認定事実(3)アのとおりであったこと,平成21年10月8日に
ZがM部長に対し,Kの対応について「あまりに非協力的な態度に私
も我慢の限界です。Jなどと記載したメールを送信していること(申28
の1),原告の入社後も,前記前提事実(5)ウ及びエ,同(9)オなどのよう
にKの対応につき顧客や社内から苦情等が寄せられていたこと,O部長
が,Kについて足りないスキル等を原告にリストアップさせた上で,原
告が作成した資料を用いてKに対してサポート品質向上のための指導を
行っていたこと(前記前提事実(5)オ,カ)などの事情を総合すれば,原告
入社前の段階から,Kのインストールサポートでの対応には社内的にも
社外的にも問題があり,技術部やその他の関連部署との信頼関係も築かれ
ていない状況であったと認めるのが相当である。
したがって,Kが従前からインストールサポート業務を問題なくこな
していた旨のO部長らの証言又は陳述は,上記の認定事実に反し,かつ,
これらの証言又は陳述を裏付ける的確な証拠も存しないから,信用できな
いというほかなく,被告の上記主張は理由がない。
(イ)原告の業務負担について
前記(ア)の認定事実を踏まえれば,Kと二人体制でインストールサポー
トを行っていた原告の業務量が多くなるのは当然とも解されるところであ
り,原告が主張する業務過多なる状態は協調性のない原告がKとの協業
を拒絶したために生じたものにすぎない旨の被告の主張は,前記(Y)の認定
に反し,採用できない。
イ 原告とKとの関係悪化について
被告は,Kのパワハラの訴えは正当な権利行使であり,原告及び、Kの
関係悪化は,単なる個人的な好き嫌いの感情を超えないものである旨主張す
る。
しかし,甲58ないし60号証及び証人Oの証言(証人O・9,34ペー
ジ)によれば,被告の前身会社でインストールサポートに従事していた際の
原告については全般的に高い評価がされていたと認められること,前記ア
(Y)のとおり,Kによるインストールサポートについては,原告の入社前
から社内的にも社外的にも問題があり,技術部その他の関連部署との信頼関
係も築かれていない状況であったと認められること,原告は,入社後間もな
くしてKについての上記状況を認識しKと二人体制でインストールサ
ポートに従事することに不安を感じつつも,状況改善のため,Kの社内に
おける信頼関係の回復に向けた具体的な提案等を行っていたこと(前記認定
事実(3)ア),また,平成22年11月17日にO部長からチームリーダー
に指名された際には納得できない気持ちを抱きつつも,Kの担当分として
割り振った依頼案件を様々な方法でKに指示し,顧客への対応が不十分な
場合には適切な対処方法について情報を提供するなどしていたこと(前記認
定事実(4),(5)ウ,オ)等の事情を総合考慮すれば,原告は,Kと2人体
制で円滑に業務を遂行するため,与えられた役割を果たそうと努めていたと
認められるのであり,原告とKとの関係悪化は,被告が,インストールサ
ポートを前記ア(ア)のとおり問題の存するKと原告との二人体制とした上
で,原告をチームリーダーに指名し,Kに対する指示・指導等を専ら原告
に行わせていたことに起因するものと解するのが相当であり,これを原告の
個人的な好き嫌いの感情によるものに過ぎないとする被告の主張は,実際の
事実経過に沿わない主張であり,理由がないというほかない。
ウ 原告入社の際の原告に対する説明について
被告は,原告の採用に当たってはKとのコミュニケーションを適切に行
うことができるかを原告に確認している旨主張し,O部長も,原告の採用前
に原告に対し,Kにつき「インストールサポート業務を十分にこなしてい
ける能力はあるがコミュニケーション能力としては少し得意でないところ
問ある。」旨の説明を数回行ったと述べる(証人O・10頁)。
これに対し,原告は,O部長からKに関する事前の説明はなかった旨述
べる(原告本人・4569頁)が,そもそも,被告は,Kにつき,社
内におけるコミュニケーション能力の多少の改善は要するものの業務に支
障を生ずる程ではなかったと主張するのであるから,原告に説明したとする
Kに関する事情もその限度にとどまるはずであり,実際,O部長の上記証
言における説明内容もその限度にとどまっているところKに関する問題
の実情は前記ア(ア)のとおりであるから,被告の主張によっても,O部長が
原告の採用に当たりKに関する問題を原告に説明していたといえないこ
とは明らかである。なお,仮に被告が原告に対して事前にKに関する問題
を説明していたとしても,前記(1)のとおり,被告が原告に対し,業務の遂
行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して労働者の心身の健康を損な
うことがないよう注意する義務を負うことに変わりがないことはいうまで
もない。
エ 小括
以上によれば,原告の業務負担の増加や原告とKとの関係悪化の原因に
ついては,原告及び、Kの二人体制で,かつ,原告がチームリーダーに指名
されてインストールサポートを担当していたという業務遂行上の事情によ
るものと認めるのが相当であるから,被告は,原告に対し,これらの業務に
伴い疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して原告の心身の健康を損なうこと
がないよう注意する義務を負うというべきである。よって,専ら原告の協調
性の欠如及び個人的な好き嫌いの感情によるものであって被告が一定の対
応をとるべき義務は存しない旨の被告の主張は,理由がない。
(3)被告による注意義務違反の有無について
被告は,原告とKとの聞の不和及び紛争に対してO部長が時間を割いて対
応策を検討・実施するなど最善の努力を尽くした旨主張し,O部長も,原告及
びKと頻繁に面談し,両者を分離して第三者を相談役に入れる体制を整え,
原告の座席の移動も事後承諾の形で認め,原告の異動についても他部署に掛け
合うなど,可能な限り原告の状況を考慮して対応した旨述べる(乙9・4頁,
証人O・16頁から20頁まで)ので,以下では,被告の具体的な対応につい
て検討した上で,注意義務違反の有無について検討する。
ア チームリーダーの指名について
前記認定事実(3)ア及びウのとおり,O部長は,原告の入社後間もなくの頃
より,原告から,Kの問題点や実情について具体的な報告をしばしば受け,
その改善を求められていたのに対し,まず,当時有期雇用契約の従業員であ
った原告をチームリーダーに指名し,Kに対する業務の指示及び指導を原
告に行わせることとしている(前記前提事実(4))が,かかる対応は,前記(2)
ア(ア)において述べたKに関する問題の対応を原告に全面的に担わせるも
のであって,原告からO部長に報告されていた実情等(前記認定事実(3)ア,
ウ等)を踏まえれば原告に相当な負担をかけることが容易に想定されるから,
O部長が,原告の負担を十分に考慮した上で上記の対応をしていたものとは
直ちに評価し難い。なお,被告は,原告の要望を受け入れてチームリーダー
に指名した旨主張し,O部長も概ねこれに沿う旨述べる(乙9・3頁,証人
O・12頁)が,入社して1か月余りであり,かつ,当時は有期雇用契約の
従業員であった原告が自らチームリーダーを望むとは考えにくく,原告自身,
チームリーダーに指名された際の打合せのノートに,「なぜこうなるのか」
「おかしい」などと走り書きをしており(甲53の4),また,O部長も,
「原告からの要求でもあった」旨述べる一方で「チームリーダーということ
を誰から言い出したかに関して,あまりよく覚えていない。」旨述べている
こと(証人O・11,12頁)に照らしても,原告が要望した旨の被告の主
張は採用できない。
イ Kによるパワハラの訴えについて
前記認定事実(5)のとおり,原告は,チームリーダーに指名された後も,原
告とKとの業務分担が不均衡になっていること,Kに仕事を割り振って
も自分の仕事でないなどと言って応じないこと,Kと仕事をすることは難
しく自分(原告)にKの指導はできないこと,Kに対して社内外から苦
情等が寄せられ,その苦情対応が原告に回ってくること,Kに仕事を任せ
られない状況であるため他部署への異動を検討してほしいこと,Kとの話
し合いは意味がないためサポート体制を変更してほしいことなどを繰り返し
O部長に訴えていたところ,この間,O部長が原告やKと打合せを行って
いた事実は認められる(前記前提事実(5)ア,カ)ものの,O部長が配置転換
やサポート体制の変更等について何らかの具体的な対策を検討し,又は実行
していた様子はうかがわれない。
そして,平成23年8月下旬には,Kが原告からパワハラを受けたとし
て被告のコンブライアンス機関等に訴え出るという出来事が生じ,人事部に
よる技術部等への聞き取り調査の結果,パワハラの事実はないと判断された
が(前記認定事実(6)),このような出来事が生じたのは,主として,インス
トールサポートを原告とKとの二人体制とした上で原告をチームリーダー
とし,Kへの指示・指導を全面的に原告に担わせることとし,原告から,
Kの指導は無理であるとしてサポート体制の変更等が繰り返し要求されて
も,上記の体制がそのまま維持されてきたことに起因すると解するのが相当
である。
ウ 平成23年10月及び平成24年3月のサポート体制の変更について
平成23年10月には,3か月間の暫定的なサポート体制として,技術部
のグループリーダーであるTを調整・相談役とし,原告及びKは製品別
の毎月のローテーションによりサポート業務を分担することとされた(前記
認定事実(8))が,Tを調整・相談役としたことが効果的に機能しなかった
ことはO部長も認めるところであり(前記認定事実(8)証人O・39頁)
また,原告及びKが互いに他方の不在時には全てをカバーする体制とされ
ている点で,基本的に原告とKとの二人体制が維持されているといえる。
そして,前記認定事実(9)エのとおり,平成24年3月上旬頃から新たなサポ
ート体制がとられたが,原告及びKの分担割合が当初から不均衡である上,
前記認定事実(9)ア及びカによれば原告のパックアップを技術部が行うこと
とし,もって原告とKとを業務上より明確に分離し,かつ,原告のパック
アップを強化する体制とすることも可能であったと解されるところ,O部長
はあくまでKを原告のパックアップとする体制を維持している。そして,
その後も,原告からKによるパックアップに問題があることが指摘され(前
記認定事実(9)オないしキ,ケ),また技術部のZからはパックアップを引
き受ける旨の申出がされていたにもかかわらず,O部長は特段の対応をとっ
ていないが,上記のように原告や技術部からの要望等を受けながらなお原告
のパックアップ体制を変更しなかったことについて,O部長がその要否や代
替策の有無等を十分に検討していたとの事情はうかがわれない。
エ 被告による注意義務違反の有無について
以上に検討した被告の具体的な対応を踏まえ,被告による注意義務違反の
有無について検討する。
前記イのとおり,Kが原告をパワハラで訴えるという出来事が生じたの
は,主として,インストールサポートを原告とKとの二人体制とした上で
原告をチームリーダーとする体制が維持されてきたことに起因するものと解
されるのであり,人事部においてパワハラの事実はないと判断されたこと(前
記認定事実(6)キ)も踏まえれば,この出来事の発生に関して原告に特段の帰
責性はないというべきである。
本件のように二人体制で業務を担当する他方の同僚からパワハラで訴えら
れるという出来事(トラブル)は,同僚との問での対立が非常に大きく,深
刻であると解される点で,客観的にみても原告に相当強い心理的負荷を与え
たと認めるのが相当であり,原告自身,原告をパワハラで訴えたKと一緒
に仕事をするのは精神的にも非常に苦痛であり不可能である旨を繰り返しO
部長らに訴えているのであるから被告は上記のように強い心理的負荷を
与えるようなトラブルの再発を防止し,原告の心理的負荷等が過度に蓄積す
ることがないように適切な対応をとるべきであり,具体的には,原告又は
Kを他部署へ配転して原告とKとを業務上完全に分離するか,又は少なく
とも原告とKとの業務上の関わりを極力少なくし,原告に業務の負担が偏
ることのない体制をとる必要があったというべきである。この点,原告は,
少なくとも原告のパックアッフを技術部が担当することとする体制への変更
を繰り返し要望していたところ,前記のとおり,技術部からも原告のパック
アップを技術部が担当する案が出され,また,Zからも個人的にパックア
ップを引き受けてもよいとする申出がされていたのであるから,原告の心理
的負荷等が過度に蓄積することがないように原告の要望に添う方向でサポー
ト体制を変更することが困難であったとは認め難いところ,前記ウのとおり,
O部長はかかる対応をとっておらず,この点について,O部長がその要否や
代替策の有無等を十分に検討していたとの事情はうかがわれない。
そうすると,O部長が,原告に対し,その心理的負荷等が過度に蓄積する
ことがないように注意して指揮監督権限を行使していたと認めることはでき
ないから,使用者である被告としても,被告が原告に対して負う注意義務(業
務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して心身の健康を損なうこ
とがないよう注意する義務。前記3(1))を果たしていないと認めざるを得な
いというべきである。
(4)被告の法的責任
前記(3)エのとおり,被告は,使用者として原告に対して負う注意義務に違
反したものと認められるから,当該義務違反により原告に生じた損害について,
民法415条に基づき賠償すべき責任を負う。
また,前記(3)エのとおりO部長は,心理的負荷等が過度に蓄積すること
がないように注意して原告に対する指揮監督権限を行使していたとは認められ
ないところ,原告からO部長に対し,状況の報告や要望等がメールで繰り返し
伝えられていたことからすれば,O部長は,原告の業務負担の状況や,Kと
の関係に関して原告が精神的にも苦痛を感じていること等を認識し,又は少な
くとも認識し得たものと認められるから,O部長がこのような認識を持ちなが
ら,上記のとおり原告に対する指揮監督権限を適切に行使しなかったことにつ
いては過失があるといわざるを得ない。したがって,O部長の使用者である被
告は,原告に対し,前記(3)エの注意義務違反により生じた損害について,民法
715条に基づき賠償すべき責任を負う。
4 損害
原告による未払時間外割増賃金と同額の付加金請求については,前記4におい
て述べたとおり被告が原告の未払時間外割増賃金支払請求を認諾している以上,
認める理由がないというほかない。
5 その他
原告による未払時間外割増賃金と同額の付加金請求については,前記4におい
て述べたとおり被告が原告の未払時間外割増賃金支払請求を認諾している以上,
認める理由がないというほかない。
第4 結論
以上によれば,原告の本件請求は,主文の限度で理由があるからこれを認容す
ることとし,その余は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第36部
裁判官 松 田 敦 子
東京地方裁判所民事第36部
裁判所書記官 谷 口 泰 政