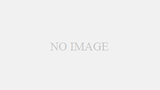訴 状
平成25(2013)年6月25日
東京地方裁判所 民事部 御中
原告訴訟代理人弁護士 志 村 新
原 告
〒160-0004 東京都新宿区四谷1-2 伊藤ビル
東京法律事務所(送達場所)
電 話 03-3355-0611
FAX 03-3357-5742
原告訴訟代理人弁護士 志 村 新
〒160-0023 東京都新宿区西新宿六丁目10番1号
被 告 アンシス・ジャパン株式会社
代表者代表取締役 馬 場 秀 実
賃金等請求事件
訴訟物の価額 金7,000,000円
貼用印紙額 金38,000円
請求の趣旨
1 被告は原告に対し,金1051万7968円及び内金351万7968円に対する平成25年2月7日から支払い済みまで年14.6%,内金348万2032円に対する同日から支払い済みまで年5%の各割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決並びに第1項につき仮執行の宣言を求める。
請求の原因
第1 当事者ら
1 被告
被告は,米国法人ANSYS, Inc. の100%子会社として平成13(2001)年に設立された日本法人が,その後,数社の買収を経て平成22(2010)年8月に設立した資本金1000万 円の株式会社で,コンピュータのソフトウェアの開発・販売,コンピュータのソフトウェアに関するマーケットリサーチ・保守サービス・コンサルティングその 他の業務を目的とし,肩書地(登記上の本店所在地)に東京本社を,大阪市内に大阪営業所をそれぞれ置いており(被告の商業登記簿謄本及び甲1=被告のウェ ブページ),平成24(2012)年12月現在の従業員数は約140名である。
2 原告
原告は,平成22(2010)年10月1日に被告に従業員(当初は雇用期間を同日から1年間と定められ,翌平成23(2011)年7月1日からは期間の定めなく)として採用され,被告技術部に所属して「インストレーションサポートエンジニア」の業務[1]に従事していたところ(甲2の1・2=雇用契約書),後述する経過により平成25(2013)年2月6日付で被告を退職するに至った労働者である(甲3)。
第2 未払時間外割増賃金請求権
1 時間外割増賃金の不払い
(1)被告の就業規則(甲4)第21条は,始業時刻午前9時30分,終業時刻午後6時,休憩時間正午から午後1時とし1日7時間30分を所定労働時間と定め,同23条は土曜日・日曜日,国民の祝日及び年末年始(12月29日から1月4日)を休日と定めている。
また,被告の就業規則(甲4)40条の「社員の給与は,別に定める給与規程により支給する。」との定めにもとづく被告の「給与規程」(甲5)は,その11条1項において,ポジション等級[2]4等級以下の者に時間外・休日・深夜労働手当を支払う旨を定め,同条2項においてその支払時期について後記のとおり定めている。
(2)被告は原告に対し,法定労働時間を超える労働及び休日労働を行った場合について支払うべき時間外割増賃金を,平成22(2010)年12月24日支給分を除き一切支払ってこなかった。
2 賃金の支払時期等に関する定め及び原告による支払催告等
(1)被告の前記「給与規程」(甲5)5条は,
「月の給与は,毎月1日から起算し,当月末日に締め切って計算し,当月25日(支払日が休日の場合はその直前の営業日)に支払う。」
と規定し,同11条2項は,
「時間外労働手当・休日労働手当・深夜労働手当は毎月1日から起算し,末日に締め切って計算し,翌月25日に支払うものとする。但し,当該支払日が会社の所定休日にあたる場合は,その直前の営業日に繰り上げて支払うものとする。」
と定めている。
(2)原告は被告に対し,平成25(2013)年3月19日到達の原告代理人作成の書面により,平成23(2011)年2月1日以降分の時間外割増賃金等の支払を催告した(甲6の1・2=「通知書」及び配達証明書)。
3 支払われるべき割増賃金額
(1)被告は原告に対し,前記「給与規程」にもとづき月例賃金として平成23(2011)年2月1日から平成24(2012)年3月末日分まではX円(甲2=雇用契約書),同年4月1日以降分はX円(甲7=同日付「給与辞令」)を支払ってきた。
したがって,原告について支払われるべき割増賃金額の時間単価は,別紙「未払残業代請求目録」1枚目上部「時間単価」欄記載のとおりとなる。
(2)原告の平成23(2011)年2月1日以降の各月日ごとの就業開始・終了時刻及び時間外労働を含む労働時間数は,別紙「未払残業代請求目録」2枚目以下のとおりである。
(3) 上記「(1)」の時間単価及び上記「(2)」の時間外労働時間数にもとづき,原告について支払われるべき割増賃金額を算出すると,平成23(2011)年 2月1日分以降の各賃金支払い期日における金額は,別紙「未払残業代請求目録」1枚目の「月間未払時間外手当」欄最下段記載のとおり合計351万7968 円となる。
第3 損害賠償請求権
1 被告による不法行為乃至債務不履行責任
(1)職場において労働者に対し,職務に関連して精神的又は身体的な苦痛を与えることにより,心身の安全,行動の自由などの利益或いは権利を侵害する行為は,不法 行為に該当し,その行為者は,当該労働者に対しこれにより被った損害(精神的苦痛を受けたことによる慰謝料,退職せざるを得ないこととなった場合の得べかりし賃金相当額の逸失利益など)を賠償する責任を負う(同法709・710条)。
上記のように職務に関連して行われた不法行為による被害については,その行為者の使用者もまた,当該行為者の選任・監督について相当の注意をしても損害の発生を避けられなかった場合を除き,損害賠償の責任を負う(同法715条)。
また,使用者は,その雇用する労働者に対し,労働契 約上の義務として安全配慮義務を負っており(労働契約法5条),その一環として労働者が労働しやすい職場環境を整える義務を負っている。上記のような不法 行為を放置することはこの義務に違反するもので,使用者は,故意又は過失の有無を問わず,これにより労働者が被った損害を債務不履行に基づき賠償すべき責 任を負う(民法415条)。
被告は,以下に述べるO部長による原告に対する不法行為を放置したことにつき,O部長の使用者として不法行為責任を負うとともに,原告の使用者としての債務不履行責任を負う。
(2)被告におけるインストレーションサポートエンジニアの業務は,以前は訴外K■■(以下「訴外K」という)が担当していたところ,顧客及び技術部のエンジニアらとの間でトラブルが頻発するなど業務に支障が生じていた。
原告は,すでに平成18(2006)年1月1日から平成19(2007)年5月末日まで被告の前身であるフルーエント・アジアパシフィック株式会社に正規 従業員として在籍し,インストレーションサポートエンジニアの業務に従事していた経験があったことなどから,平成22(2010)年10月1日から勤務を 開始してまもなくから訴外Kの問題点に気付き,原告及び訴外Kが所属する技術部のO部長に対し状況を報告するとともに改善策をとるよう求めた。
しかし,O部長は,その後も原告が状況を報告しつつ改善策をとるよう繰り返し求め続けたにもかかわらず,事態を放置し続け,このため訴外Kが担当業務を放棄するなど,状況は改善されないどころか却って悪化する有様であった。
(3)平成23(2011)年8月に至り,訴外Kは,O部長不在のさいに,自らの担当業務を放置し続ける一方で,原告がサポート中の顧客からの連絡を待って一時離席したわずかな隙に,突如としてこの顧客に対するサポートを開始し,自分が解決した旨を主張するに至った。
このため,同月18日,原告は訴外Kに対し,記 録を残す意味でも技術部のマネージャーを含む全員を宛先に加えたメールで,訴外Kの上記顧客に対する対応には問題があることを指摘して批判した。ところ が,これに対し訴外Kは,この指摘・批判自体がパワハラ行為であり,さらには実際には自らが全く仕事をしようともしないにもかかわらず原告が仕事をさせて くれないなどと虚偽の事実をO部長及び被告コンプライアンス機関に訴え出た。
これを受けて,同年9月に入り,人事部により技術部所属従業員らの 聞き取り調査が行われ,訴外Kの勤務態度やこれまでのトラブルの事実が改めて明らかとなった。原告に対する聞き取りの際には,R前人事部長が原告に対し 「こんな状況になるまで誰も報告しなかったのか」と驚きを示すとともに,訴外Kとは一緒に業務を担当させることは二度とないとまで述べた。
ところが,同月半ばに至ると,R人事部長とO部長は原告に対し,再び訴外Kとともに従来どおりの業務を行いながら訴外Kの指導をするよう要請した。これに対し 原告が異議を述べたところ,指導だけは他部署の者に代わってもらえることとなったが,今後の訴外K指導のためにとしてビジネスリーダーシップ研修の受講を命じられた。
以後も原告は,O部長に対し,訴外Kと協同して業務を遂行することは不可能であり,再発防止のための配置転換も必要であること,何の対策もなければ結局は自分が退職するしかない旨を何度も訴え続けた。
(4) 翌平成24(2012)年2月,この間に退職者が相次いだことなどから他部署からも改善要求が上がった結果,米国本社による聞き取り調査が行われ,原告も これまのでの日本の状況を伝えた。しかし,O部長は事態の改善に努めるどころか聞き取り調査に応じた人物の割り出しに狂奔するなど自らの保身とも言うべき 対応に終始し,人材の流出を招く結果となった。
同年3月12日からは,原告と訴外Kとで担当製品を区分けした業務分担(8割以上が原告)とされたが,これも完全な業務分担ではなく,O部長は,原告のバックアップだけは訴外Kが行うとの条件を決定した。
その後も,訴外Kは以前よりも業務が少なくなったにもかかわらず週1回以上年次有給休暇を消化し,原告の業務についてのバックアップも事実上機能せず,原告の業務量はいっそう増加した。このバックアップ体制の問題については,技術部のマネージャーらからも改善要求等が何度も上げられたが,O部長は全て拒否し 続けた。
原告は,同年10月5日には馬場社長宛に要望書も提出したが,回答すら得られないままに放置され,状況が改善されなければ辞めるしかない状況だと何度もO部 長に訴えたにも関わらず,O部長は「今後も改善はしない,ただ彼と働くか,この会社を辞めるか」と最後まで同じことを繰り返し続けた。
(5)原告は,悩みに悩んだ末に同年12月26日に至り,O部長に対し,1年以上にわたって事態の改善を訴えてきたにもかかわらず改善が図られないのでは退職せざるを得ないことを訴えたところ,O部長は原告を引き留めるどころか却って退職を促した。
このため,同日,原告はO部長宛に最終出勤日を同月28日として退職する旨を伝える電子メールを送信したところ,翌27日朝,O部長は,年次有給休暇の残日数も消化させずに退職手続を進めようとまでした。これに気付いた原告は,同日,翌平成25(2013)年2月6日付で被告を退職する旨の「退職願」(甲 3)を被告人事部に提出するに至ったものである[3]。
2 原告の損害
以上の原告に対する訴外O部長による不法行為を被告が放置し続けるなどして適切に対処しなかったために,原告が在職中に被った損害及び退職を余儀なくされたことにより被った損害は合計400万円を下回らないところ,本訴においては内金348万2032円(及び遅延損害金)の支払を求める。
第4 結論
よって,原告は被告に対し,
(1) 未払時間外割増賃金351万7968円及びこれと同額の付加金並びに未払時間外割増賃金に対する退職日の翌日である本年2月7日から支払い済みまで賃金の支払いの確保等に関する法律6条1項所定年14.6%の割合による遅延損害金
(2) 不法行為乃至債務不履行にもとづく損害賠償金348万2032円及びこれに対する弁済期後である前同日から支払い済みまで民法所定年5%の割合による遅延損害金
の各支払いを求めて本訴にいたったものである。
証 拠 方 法
甲1 被告のウェブページ
甲2の1 平成22年8月11日付「雇用契約書」
甲2の2 平成23年6月14日付「雇用契約書」
甲3 平成24年12月27日付「退職願」
甲4 被告の「就業規則」
甲5 被告の「給与規程」
甲6の1 平成25年3月18日付「通知書」
甲6の2 郵便物配達証明書
甲7 平成24年4月1日付「給与辞令」
添 付 書 類
1 訴状副本 1通
2 甲号証写 各1通
3 資格証明書 1通
4 訴訟委任状 1通
以 上
[1] 被告会社の前身である旧フルーエント・アジアパシフィック株式会社で使われていた名称で,雇用契約書に記載された職務名。ANSYS本社では「システムサ ポートエンジニア」の名称に変更されており,原告の場合も,後述する技術部のO部長にも説明のうえANSYS本社に「システムサポートエンジニア」として レポート済みで,名刺も同名称で作成済みであった。(閲覧制限により省略)
[2] 最下位1等級から最高位6等級までとされ,原告の等級は,当初は定められていなかったところ後述する平成24(2012)年4月1日付「給与辞令」(甲9)において「2」と定められた。
[3] なお,O部長は,原告の退職が確定すると,これまで一切応じてこなかった原告の担当業務のサポートを技術部全体で行うことを即決したうえ,原告を「裏切り 者」呼ばわりした。また,被告は,原告が平成25年2月6日まで在籍しているにもかかわらず,原告による被告会社のシステムへのアクセスを不能とした。